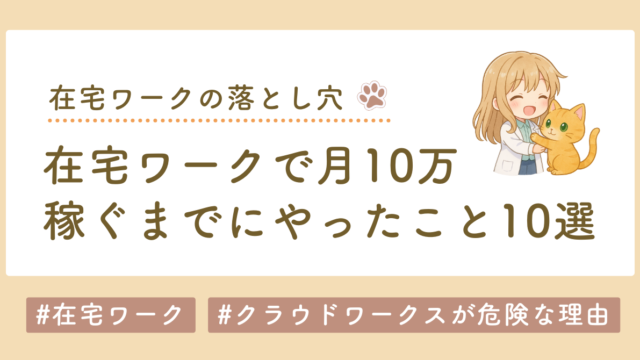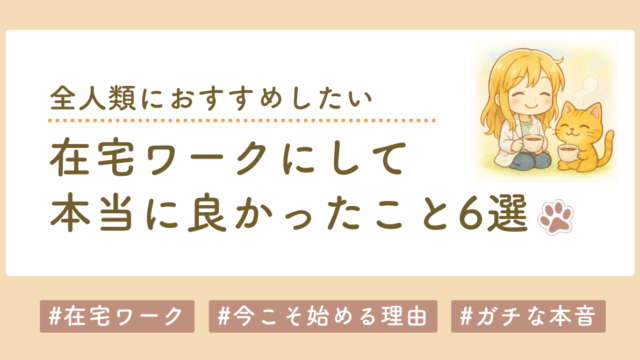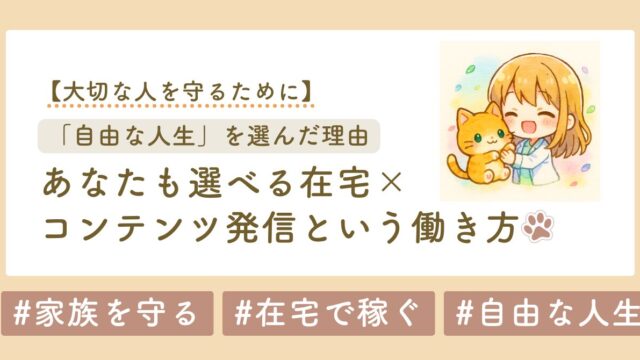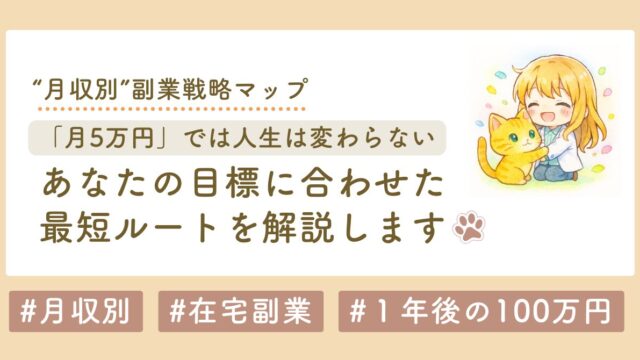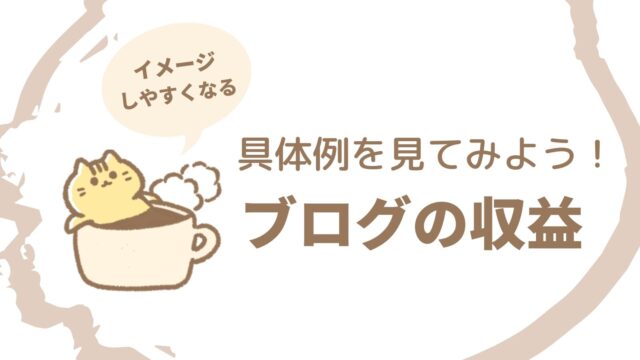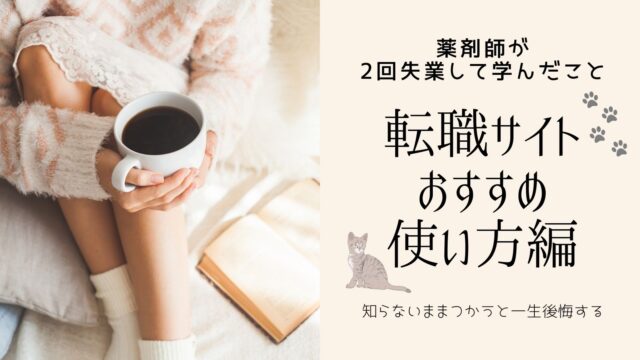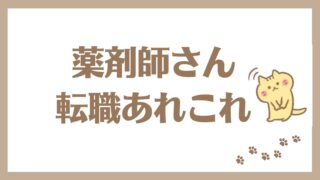こんにちは!にゃんこ薬剤師です
本記事では薬剤師の副業にブログがぴったりである理由を解説しています
この記事を書いている人の紹介↓
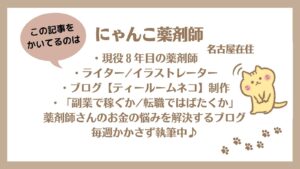
薬剤師の副業でブログが人気の理由
どうして薬剤師の副業にブログが向いているかですが
結論:SOAP薬歴の書き方とブログの書き方が類似しているからです
ブログの記事の書き方の手順
ブログを書く手順を見てみると
6つに分かれています
具体的には
- 書くキーワードを決めて検索する人物像設定する
(年齢・性別・職業・趣味・家族構成・悩み・夢・日常生活) - 検索意図や隠れたニーズを見つける
- 記事構成を考える
- 文章を肉づけする
- 文章装飾して見やすくする
- 読者に必要なコンテンツは不足していないかチェック
では、おなじみのSOAP薬歴の書き方?
SOAP薬歴の書き方と手順
S(Subjective)主観的情報
患者さんの物事の考え方
病気や薬に対する考え方を知ることができる重要な情報を記載
具体的内容:
- 患者さんからの相談事例、要望
- 患者さんの主訴(家族の代弁も含まれる)
- 体調変化などの自覚症状
- コンプライアンス状況
- 生活環境
- 嗜好
0(Objective)客観的情報
誰が見ても変わらない情報であり、処方内容、検査値、公費負担番号などの保険情報から患者の疾患などを推測する。 また、S情報と関連しそうな情報を抽出して記載しておく。
- 体質
- アレルギー歴
- 職業
- 診断名
- 他科受診
- 飲食物、嗜好品
- 家族の病歴
- 副作用歴
- 妊娠の有無(女性の場合)
- 検査値
- 併用薬
A(Assessment)分析・評価
S情報、O情報をもとに薬剤師として判断や評価したことを記載
・効果や副作用、相互作用など薬に関する評価。
・心配や不安などの患者の心理的社会的な面の評価。
(また、患者とかかわって考えたこと、思ったこと、感じたこと、感想でも可。 )
S情報とO情報が異なる時は、判断を記載する必要がある
薬物治療、健康相談、医薬品選択(販売)などで行う薬剤師の判断や選択。今後どのような方向にケアを進めるか考察する
- 相互作用
- 副作用
- 処方監査
- 重複服用
- コンプライアンス上の問題
P(Plan)計 画
S情報、O情報、A情報に基づき実際に薬剤師が服薬指導した内容、次回フォローすべき内容を記載する。
- 医薬品の選択(販売)
- 患者さんへの指導事項、情報提供
- 医師への問い合わせ、情報提供
- 調剤上の工夫
- Ep)Educational Plan 情報提供、指導など(教えたこと)
- Cp)Care Plan 疑義照会、調剤方法の変更(してあげたこと)
- Op)Observational Plan 次の薬剤師に(して欲しいこと)
薬剤師の仕事とブログの共通点①~書くことが一緒~
つまりSOAP薬歴の書き方を要約すると
- 患者と会話し人物像を把握
(年齢・性別・職業・趣味・家族構成・悩み・未来像・日常生活) - 問題点・疑問点・変化点・隠れた問題・解決策を見つける
- 薬歴構成を考える
- 文章を肉づけし書く
- 次回見る薬剤師のために分かりやすく見やすく時に箇条書きで書く
- 不足項目がないかチェック
これと
もう一度ブログの書き方を並べてみると
- 書くキーワードを決めて検索する人物像設定する
(年齢・性別・職業・趣味・家族構成・悩み・夢・日常生活) - 検索意図や隠れたニーズを見つける
- 記事構成を考える
- 文章を肉づけする
- 文章装飾して見やすくする
- 読者に必要なコンテンツは不足していないかチェック
どうでしょう
並べてみるととても似ています
とゆうかやっていることが
ほぼかぶっているように見えませんか?
薬剤師の仕事とブログの共通点②~未来を書く~
SOAP薬歴のPでは今後の計画を書きます
これは未来の患者のより良い健康的な未来を想像して、その姿に近づけていけるように何をすべきかをかく項目
これがブログの「読者の未来を想像できるように書く」のと同じ作業にあたります
読者が自分の記事を読んで
【将来どうなるのか、何が達成できるのか】
これと
患者さんが自分が服薬指導したことで【未来はどう変わっていけるか】
これが同じ作業なんです
薬剤師は患者のより良い未来のために
自分が次回何をするべきかも薬歴に書きますよね
ブログも同じ
読者の未来のために自分が書くべき内容を明確にするのです
薬剤師の仕事とブログの共通点③~教育する~
ブログに必要なマネタイズ能力の一つが
「読者の教育」です
- 有益な情報
- 必要な情報
- 未来のために知っておいてほしい情報これらを書くことで教育を行います
これも薬剤師が普段業務でしていることと
似ています
患者さんに
- 必要な知識
- 大切な情報
- 気を付けてもらうべき点を説明し未来に不利益が起こらないよう説明・教育する
やっていることは
ブログのマネタイズと一緒なんです
結論【薬歴かける】なら【ブログは書ける】
つまりSOAP薬歴を
普段の業務でわずか10分15分で書いてしまう薬剤師は
ブロガーにとても向いているといえます
薬剤師の仕事は【ブログ向き】
まとめると
- そもそもの薬剤師の仕事内容とブログ執筆内容がとても似ている
だから
- 副業でブログをやることは薬剤師にとって難しいものではない
何故か
「患者を把握・データを分析・必要な情報を整理・計画を立て患者に教育・説明する」
薬剤師が普段行っているこの仕事内容そのものが
ブログの執筆活動内容そのものなのですから
- ブログを書くのに必要な考え方はもう訓練されている
- 考え方はもう身についている
それが薬剤師です
違う点はここだけです
おさえておきましょう
- 薬剤師は服薬指導で患者からお金をもらう
- ブログはクリック型広告やアフィリエイトでお金をもらう
クリック型広告ってなに?
アフィリエイトってなに?という質問には
以下で詳しく解説しますね
ブログにはクリック型広告を貼って稼ごう
有益な情報には、利益が発生します
ブログを始めたら有益な情報の下に広告を貼ってみましょう
読者がなるほど!と共感すれば
あなたの広告がクリックされます
それでお小遣いがかせげるようになるのがブログの稼ぎ方です
アフィリエイトしてお小遣いを稼ごう
広告のほかにもスクールの紹介などもあり
アフィリエイト記事ではリンク先を貼り付けて
読者に有益だと思う記事をあらかじめ貼っておくものです
これでアフィリエイト完成です
色々な貼り方ができ
ブログのテイストを損なわないようにそっと添えることもできます
☆薬剤師限定☆80%以上の方が希望条件で転職!あなたのご希望は?
実際に見て
![]() 【アフィリエイト】のイメージはつきましたか?
【アフィリエイト】のイメージはつきましたか?
注意点は、自分がおすすめできないものは載せないこと
選ぶのは常に読者さんですので
添えるくらいにしておくのがポイントですね
どうして副業におすすめは【ブログ】なの?
ブログ以外にも副業にはいろいろありますが
なかなか少額から開始できて、こんなに
メリットばかりの副業もなかなかないのも事実です
初心者が副業でYouTubeをするのはお金がかかる
よくYouTube動画や中国せどりもおすすめされますが
YouTube動画を作るには【教材】を購入して進める方が効率がいいのと、YouTube動画は登録人数が1000人以上いないと収益は発生しません
なかなか素人には厳しい世界です
文章の構成力も必要ですので、必然的にクラウドワークスやココナラで【依頼】して始めることになりますので、【動画編集】さんを雇ったりと、なかなかな初期投資は必ず必要となってくる【副業】なのです
中国せどりなんかも在庫をかかえておかなければなりませんし
取引の密なやりとりもなかなか大変です
けれどブログにはそんな初期投資も在庫もいりません
簡単にブログのメリットをまとめてみました
副業でブログをやる9つのメリット
- パソコンがあれば家で副業できるから(移動時間がない)
- 勤務時間が存在しないから(スキマ時間にできる)
- コミュニケーションが必要ないから(記事を書いて広告を貼るだけ)
- 不労所得になりうるから(一度収益化できたらあとは寝ててもOK)
- 文章力も身につくのでライター事業もできるようになる(メディカルライターもできる)
- 在庫を抱える心配がない
- 初期コストがかからない
- スクール等での学習が不要
- 失敗時のリスクがない(仮に上手く行かなかったとしても失うものはない)
ブログにはテンプレートがあるから安心
①ブログなんて【文系じゃなきゃ書けない】はウソ
実はこれは間違い
ブログは過去の自分への記事・手紙のようなものなので
失敗談・体験談をかいて解決策をかけば誰でもかけるんです
文が不得意でも箇条書きでOK
むしろ箇条書きが推奨されています
【日本語は書けば書くほどNG】
これがブログの鉄則!です
②【文を考えるのはめんどくさいでしょ?】はウソ
ブログには文章のテンプレートがあるから実は簡単なんです
むしろ文章の型はきまってるんです
自由に書くより型に沿って書くことをおすすめします
【ブログの文章の型】はこれ一択!
気になる方はこちらからどうぞ
はじめは興味のある分野からじょじょにブログを書いて
小銭稼ぎしちゃいましょう
結論 薬剤師の副業にブログがぴったり!
実際興味がでてきた方のために
ブログの効果的な始め方を載せておきます
こんなに本業と似た副業があるなら
やらない手はないですね!ということで
「薬剤師の副業はブログがおすすめ」でした
当サイトでは
「副業で稼ぐか・転職ではばたくか」薬剤師さんのお金の悩みを解決するブログ記事を多数執筆しています
新しい記事は毎週土曜日に執筆されます
よければまた見に来てくださいね!