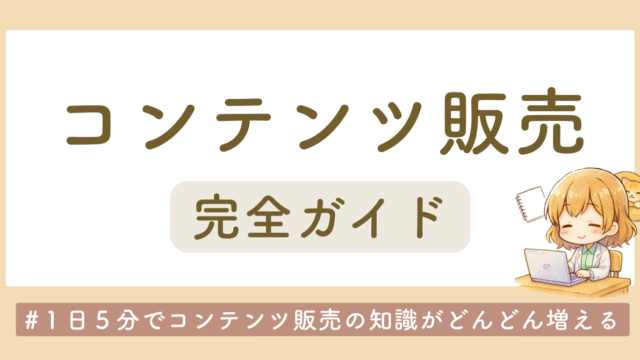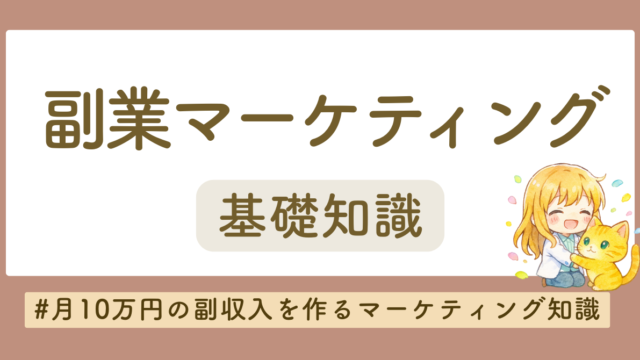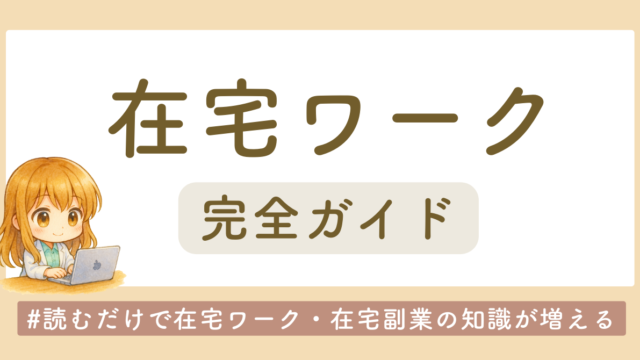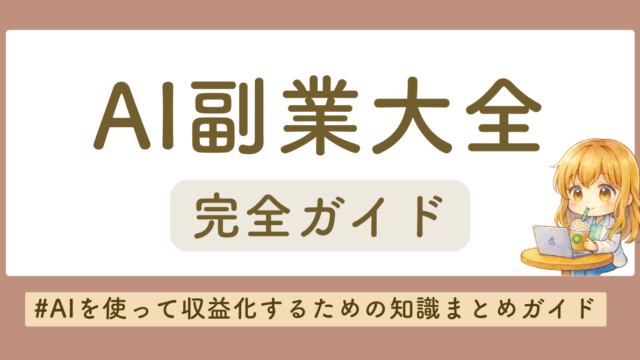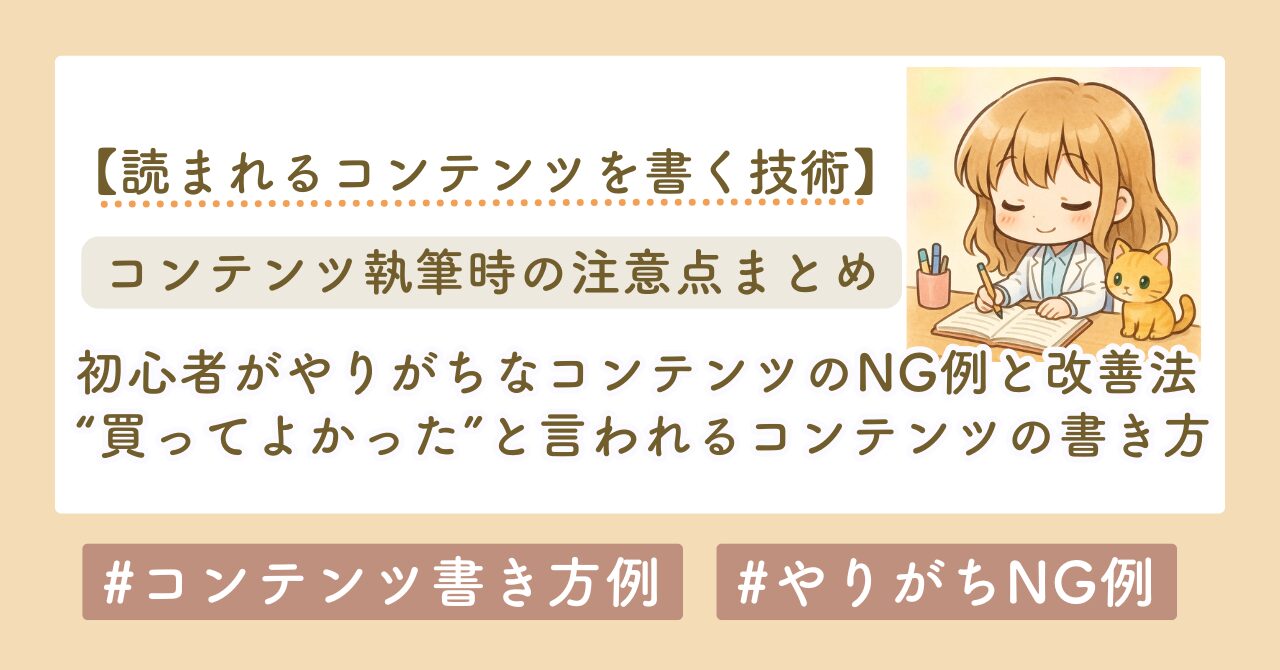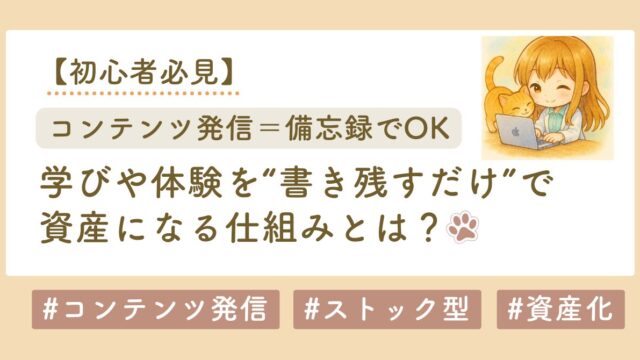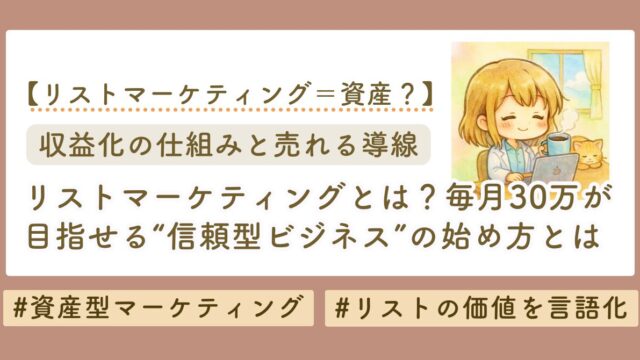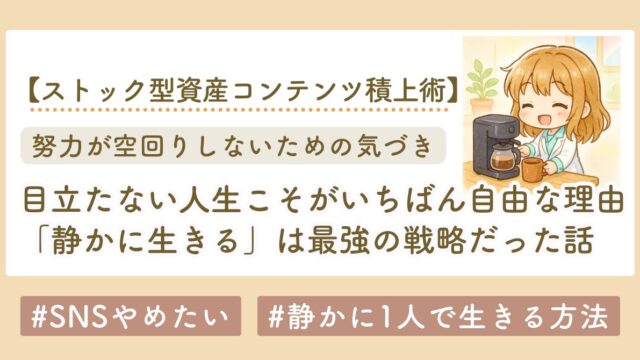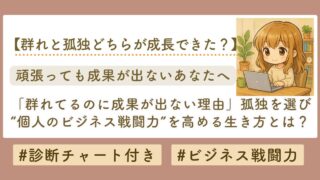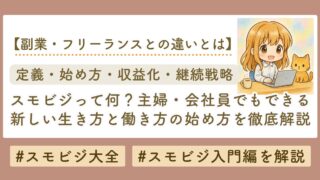はじめに:なぜ「コンテンツの書き出し」で止まるのか?
こんにちは、ねここです。
この記事を読んでいるあなたは、もしかすると「コンテンツを書こうとしたけど、手が止まってしまった…」そんな経験があるのではないでしょうか?
たとえばこんな感じです。
-
リサーチは終わった
-
ターゲットも決まっている
-
売りたい商品も明確になった
-
でも、どこから書き始めればいいか分からない…
こういう状態、実はすごく多いです。
私がコンテンツ制作を教えているクライアントさんたちも、同じようにつまずく人が何人もいます。
そしてこれは、「文章力がないから」ではありません。
書けないのは、あなたのせいじゃない
「文章力がない」「センスがない」
と自分を責めてしまう方が多いのですが、それは大きな誤解です。
実際には、“書き出す前にやるべきこと”が明確になっていないだけなんです。
この記事でわかること
この記事では、以下のような悩みを解決する内容をお伝えします。
| よくある悩み | この記事で得られること |
|---|---|
| 何から書き始めればいいのか分からない | 書き出しの鉄板テンプレートがわかる |
| 最初に何を書いたら読まれるのかわからない | 「再定義」で読者の心をつかむ方法がわかる |
| 書きながら自分でも何が言いたいかブレる | 全体構成テンプレでブレずに書き進められるようになる |
| 読まれないコンテンツになってしまう | 読者が最後まで読んでくれる「読みやすい構成」が身につく |
この記事は
-
初めてコンテンツを書く方
-
noteやBrainに出してみたけど反応が薄かった方
-
コンサルや講座で習った知識はあるのに、形にできない方
-
ライティングは苦手だけど、人の役に立つ情報は持っている方
に特に役立つ記事になっています!
第1章:コンテンツは「書き出し方」で9割決まる
なぜ最初の一文が重要なのか?
コンテンツにおいて、最初の書き出しはものすごく大切です。
これは、いわば「レストランの入り口」と同じで
見た目がオシャレでメニューもわかりやすかったら、入りたくなりますよね。
でも、入り口がゴチャゴチャしていたり、メニューに何があるのか分からなかったら…
お客さんは入らずに大半スルーしてしまいます。
文章も同じです。
最初の一文で「なんか難しそう」と思われたら、スクロールすらしてもらえませんし
悪い印象を持たれてしまうことになります。
初心者がよくやるNGな書き出し
実は、初心者さんがよくやってしまうのが、こういった書き出しです。
NG例①:いきなり結論だけを書く
「ライティングとは、ターゲットに刺さる文章を書くことです。」
一見わかりやすそうに見えますが、これでは「ふーん、そうだよね」で終わってしまいます。
NG例②:自分の体験ばかり話す
「私が初めてnoteを書いたのは2022年の春のことでした。」
これも悪くはないのですが、読者が置いてけぼりになりがちです。
自己紹介を聞きに来ているわけではないので、途中で離脱される可能性が高まります。
じゃあ、何を書けばいいの?というと
それが次の章で解説する「再定義(リフレーミング)」という書き方です。
この「再定義」を使えば、
読者の注意を引きながら、思わず続きを読みたくなる導入が作れるようになります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 書き出しは「入り口」 | 入り口で失敗すると読まれない |
| NG:知識の羅列だけ | 「それ知ってる」でスルーされる |
| NG:自分語りだけ | 読者にとってのメリットが見えない |
| 正解:「知ってるワード」を再定義 | 知識がある人にも刺さる切り口で、続きを読ませることができる |
次の第2章では、「再定義ってどうやるの?」という疑問にお答えします。
-
なぜ“再定義”が効果的なのか
-
どんな言葉を選べばいいのか
-
初心者でも使えるテンプレと例文
こういったことを丁寧に解説していきます。
第2章:再定義で読み手の“思い込み”を裏切る技術
再定義(リフレーミング)とは?
「再定義」とは、読者がすでに知っている“言葉”に、別の意味を与えて再説明することです。
たとえば「ダイエット」だと
多くの人は「体重を落とすこと」と思っていますが、こう言い換えることができます。
「ダイエットとは、“習慣を整えて人生のリズムを変えること”なんです。」
すると読者は、「えっ?なにそれ?」と興味を持って続きを読みたくなります。
なぜ“再定義”が必要なのか?
初心者さんがつまずく理由のひとつに、
「読者に何を伝えたいか」が伝わる前に、ページを閉じられてしまうことがあります。
これは、「伝え方の順番」が間違っているせいです。
多くの人は、こう書きます。
よくある失敗パターン
「このコンテンツでは、〜〜のテクニックを5つ紹介します」
→ 読者:「テクニックの話なら、もう他の人も書いてるしな…」
読まれる再定義パターン
「ライティングとは、テクニックを覚えることではありません。
本質は“読者の気持ちを動かす構成を組めるか”にあります。」
→ 読者も、これなら「おっ、ちょっと違う視点かも?」「みてみよう!」と思いますよね。
つまり再定義はお客さんのやる気を底上げしてくれるものなんです。
再定義は「最初の3行」で決まる
コンテンツを興味づけして少しでも
「この人のコンテンツや解説は読みやすい!」
と思ってもらうために
再定義を入れる場所は、導入の最初の3行以内が理想です。
なぜなら、読者は最初の3行で「読むかどうか」を判断するからです。
具体的な再定義の例
| よくある言葉 | 再定義の例文(読みたくなる表現) |
|---|---|
| 副業 | 「副業とは、稼ぐ手段ではなく“自由を買う技術”です。」 |
| セールス | 「セールスとは“売ること”ではなく“信頼を積み上げる作業”です。」 |
| コンテンツ作り | 「コンテンツとは“知識を渡す”ものではなく、“未来を見せる”ものです。」 |
| 時間術 | 「時間管理とは“やることを減らす”技術ではなく、“やらない理由をなくす”技術です。」 |
初心者でも使える再定義テンプレだと、こんな感じです。
① 一般的に〇〇とは、××だと思われています
② しかし私の考える〇〇とは、△△なんです
③ なぜなら〇〇にはこんな背景があるからです
具体的にみてみるなら↓
例文:ライティングの再定義
「多くの人は“ライティング=文章力”だと思っています。
でも、私の考えるライティングとは“お客様の頭の中でイメージを再生させる力”です。
なぜなら、人はイメージできたときに初めて『欲しい』と感じるからです。」
こんなイメージです。
「再定義」は何を再定義すればいいの?
ポイントは「読者が知ってそうな言葉」を選ぶこと
たとえば、「コンテンツの書き方」を教える記事なら、
「コンテンツ」「ライティング」「テンプレート」など、
読者が聞いたことがあるワードを選ぶのがベストです。
読者の“思い込み”を裏切るから読まれる
再定義は、読者の「思い込み」を少しだけ裏切ってあげる技術です。
この“裏切り”があることで、
読者の脳内に「予想外」「違和感」「気づき」が生まれ、文章に引き込まれていきます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 再定義とは? | 読者が知っている言葉を、新しい意味で言い換えること |
| なぜ重要? | 「それ知ってる」と思われるのを防ぎ、続きを読ませる導線を作れる |
| どこで使う? | 導入の最初の3行以内 |
| どうやって? | 「一般的には〜ですが、私の考えでは〜です」テンプレートを使う |
| 注意点 | 難しい言葉ではなく、読者が知っていそうな言葉を再定義するのが効果的 |
これ、ない人が本当に多いんですよ。
結果、つまらないコンテンツ化しちゃってるわけです。
なので、お客さんのやる気を底上げしてあげるべく、
「再定義」でドッキリを仕掛ける形でコンテンツを興味づけしながら書いてあげましょう。
次の第3章では、
「コンテンツ全体の流れ(全体像)」を最初にどうやって見せれば、読者が安心して読んでくれるのか?
について、図解やフレームワークを交えて詳しくお話していきます。
第3章:全体像を最初に提示して、読者の“安心感”をつくる技術
なぜ「最初に全体像を見せる」のか?
コンテンツを書き始めるとき、多くの人は“言いたいこと”をどんどん書いてしまいがちです。
しかし、読む側の脳は
「先が見えないこと」
に不安を感じるのです。
「この人、どこに話を持っていくんだろう?」
「結局、私は何を得られるんだろう?」
こういった不安を消すために必要なのが、
「この記事ではこういう流れで説明します」という“全体像の提示”です。
全体像を見せることで、読者は次のように感じます。
| 読者の不安 | 全体像の提示によって得られる安心 |
|---|---|
| 話がどこに向かうのか分からない | 「ゴールはここですよ」と言われて安心 |
| 今読んでいる部分が何の話なのか分からない | 「この章は全体のこの部分だ」と位置づけられる |
| 時間をムダにするんじゃないか | 「読めばこういう学びがある」と期待感を持てる |
全体像を出すと、読者はコンテンツを安心して読み進められます。
例えば私がよくコンテンツを書くときに使っているのはこういう書き方です↓
初心者さん向け:全体像を提示するテンプレ
この記事では、〇〇を達成するために、以下のステップで解説していきます。
ステップ1:〇〇とは何か(再定義)
ステップ2:〇〇の全体像をつかむ
ステップ3:〇〇のやり方(3つのポイント)
ステップ4:〇〇を実践するための注意点
ステップ5:まとめと次のアクション
実例で説明するなら
実例:コンテンツの書き方の記事なら
この記事では、「リサーチ後に書くコンテンツをどうやって構成すればいいか?」を解説します。
以下の5つのステップで進めていきます。
書き出しで注意すべき“罠”とは?
再定義で読者の心をつかむ方法
全体像を伝えて安心させる構成術
ステップバイステップで内容を伝えるコツ
書けないときの対処法とまとめ
こう書くだけで、読者の「最後まで読む理由」が生まれます。
これない人も結構多いです。
全体像がないとどうなるか?(よくある失敗)
逆にですね、以下のような書き方は、読み手を不安にさせるのでNGです。
NG①は「いきなり個別論から始めてしまう」こと。
例えば
「まずSNSで発信しましょう。次にメルマガです。」
こんな書き方をいきなりされると
読者は「え?なんでその話なの?何がゴールなの?」とわからなくなってしまいます。
NGケースの②は「全体構成がないままストーリー展開する」ことです。
例えば
「私は最初noteを始めたのですが、全然反応が取れませんでした…」
→こう言われると、 読者は
「うーん、で、どこに話が向かうの…?」となるわけです。
なので
読者は“目的地が見えている文章”を求めている
と覚えておきましょう。
コンテンツは登山と同じです。
「あとどれくらい登ればゴールか」
が分かっていれば、頑張れるのです。
逆に、先が見えない登山では不安や疲労感が先に立ってしまいます。
文章も一緒なので
ゴールと地図を示してあげることが、“読者を最後まで連れていく”ための鍵です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| なぜ全体像が必要? | 読者は「ゴールが見えないと不安」になるから |
| どこに書く? | 書き出し直後 or 第1セクションの終わり |
| 書き方のコツ | ステップごとに番号を振って構成を書くと、読者が道筋をイメージしやすくなる |
| 注意点 | 「いきなり体験談」や「突然のテクニック紹介」は迷子の元 |
次の第4章では、
「ステップバイステップで読ませる文章」の作り方について、
実例やよくあるミスを交えながら具体的に解説していきます。
第4章:ステップバイステップで“理解される”文章をつくる方法
なぜ“段階的な解説”が必要なのか?
初心者の多くが、読者に伝わらない理由はこれです。
「一気に全部、言いすぎている」
あなたも経験ありませんか?
誰かに説明していて、「なんでこの人は分かってくれないんだろう?」と感じたこと。
それ、実は相手が“理解できない”のではなくて、“情報の順番”が適切じゃないだけなんです。
例えばですが、富士山の頂上にいきなりワープさせられたら、酸欠になりますよね。
途中の「五合目」「六合目」…を経て、少しずつ高度に慣れていくから、最後まで登れるのです。
文章もまったく同じで
読者を「いきなり高度な話」に連れて行かず、一段ずつ段差をつくるのが、伝える技術です。
なので「ステップバイステップの構成」を作って書いていってください。
ステップ構成の例
ステップ1:準備(マインド・環境)
ステップ2:基礎(道具・材料・考え方)
ステップ3:実行(やってみる)
ステップ4:応用(うまくいくためのコツ)
ステップ5:定着(習慣化、継続の仕組み)
実際の構成テンプレ(例:発信講座系)だとこんな感じです。
| ステップ | 内容 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ゴールの明確化 | 「なぜこれを学ぶのか?」を先に示す |
| 2 | 準備と前提知識 | 前提知識、用語解説、最低限の環境を揃える |
| 3 | メインの実践 | 「やること」「手順」「注意点」をセットで伝える |
| 4 | 応用例・失敗例 | よくあるミスや実例を見せて、理解を深める |
| 5 | 次のステップと習慣化 | 「実践→習慣化→結果」へ導く |
各ステップに「理由」「例」「手順」をセットで書く
また、ステップごとの説明では、必ず以下の3点セットで書くのがおすすめです。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 理由 | なぜこのステップが必要なのか? |
| 例 | 具体的な実例、想像しやすい状況 |
| 手順 | 何をどうやればいいのか?順番・操作・マインドなどを明示 |
次の第5章では、
「コンテンツの価値づけ」=“なんでこれが大事なの?”を伝えるテクニックについて解説します。
読者が「普通のこと書いてるだけじゃん」と離脱しないために、
“価値を感じてもらう言葉の入れ方”をしっかり学んでいきましょう。
第5章:読者が「これは私に必要だ」と感じる“価値づけ”の技術
なぜ「価値づけ」が必要なのか?
ステップを丁寧に伝えても、読者はこんなふうに思うことがあります。
「結局、これをやることでどう変わるの?」
「ふーん、なんとなく分かったけど…で、これって私にとって本当に意味あるの?」
「知ってる内容ばっかりだったな」
このように「実践するかどうか」=「その情報に価値を感じるかどうか」で決まります。
読者は“当たり前”を軽視する
文章を書いている本人は「すごく丁寧に説明した」と思っていても、
読み手側は「当たり前のことを言われてる気がする」と感じてしまうことがあります。
ここで必要なのが、“価値づけ”=「なぜそれが重要なのか」を説明することです。
価値づけとは?(初心者向けの定義)
価値づけとは、「その情報がなぜ読者にとって必要なのか」を言語化することです。
ステップの合間や最後に「このステップがあることで、あなたはこう変われます」と伝えるのが大事です。
例:価値づけあり/なしの比較
| パターン | 内容例 | 読者の反応 |
|---|---|---|
| 価値づけなし | 「ステップ3は“文章構成”を組み立てましょう」 | 「ふーん、知ってるよ」 |
| 価値づけあり | 「構成が整っていないと、どれだけ内容が良くても“途中で離脱”されてしまいます」 | 「なるほど、それならやったほうがいいな」 |
価値づけをすると「行動率」が上がる
人は、「なるほど、それならやらなきゃ」と納得したときに、初めて行動します。
「納得 → 行動」の順です。
納得のない行動は、習慣にも成果にもつながりません。
価値づけがあると、
-
「私に必要だ」
-
「これは他と違う」
-
「自分のための情報だ」
このような感情が生まれます。
なのでコンテンツを書くときは、このような順番を大事にしましょう。
| タイミング | 内容例 |
|---|---|
| 各ステップの冒頭 | 「なぜこのステップが重要なのか」から入る |
| ステップの締め | 「このステップをやることで何が変わるか」を明確にする |
| 記事のまとめ・エンディング | 「この記事で得た知識がどう役立つか」「未来がどう変わるか」を描く |
価値づけのテンプレート例
初心者さんでもすぐに使える言い回しも、以下にまとめました。
| タイプ | フレーズ例 |
|---|---|
| 結果提示型 | 「このステップを取り入れることで、読まれる確率が2倍になります」 |
| 失敗回避型 | 「これを省くと、多くの人が『反応ゼロ』という結果になります」 |
| 実績証明型 | 「私自身、このポイントを意識しただけで月商が◯倍になりました」 |
| 他者比較型 | 「成功者は必ずこのステップを押さえています。逆に失敗者は…」 |
このように「放置すると損」「押さえると得」という両面から説明できると、読者の心に刺さります。
初心者がやりがちな価値づけミスは、このように↓
| ミスパターン | なぜダメか |
|---|---|
| 「重要です」とだけ書く | 「なぜ重要なのか?」が伝わらないと、読者は納得しない |
| 実績がぼやけている | 「すごい人だけができた話」に聞こえて、自分ごとにならない |
| 抽象的すぎる価値づけ | 「役に立ちます」「結果が変わります」だけでは具体性が足りない |
読者を置いてけぼりにしてしまうコンテンツの書き方になっています。
「未来」を見せるのが価値づけの本質
結局、読者がコンテンツを読む理由はひとつです。
「今の自分よりも、未来の自分が良くなると信じられるから」
その“希望”を言語化して見せることこそが、価値づけなのです。
次は書けないときの対処法も解説しておきますね。
-
手が止まるときにどうすればいいのか?
-
“書かないで書く”という逆転発想のテクニック
-
私自身の実体験から得た方法
などをお伝えします。
第6章:書けないときの対処法「話してから書く」
書けない…そんなとき、どうすればいい?
リサーチも終わった。構成も作った。
それでも、いざ書こうとすると手が止まる。
「この言い回しでいいのかな…?」
「なんか、文章が硬い気がする」
「書いててつまらない」
「これ、読まれるのかな…?」
こういう状態、コンテンツ制作では誰でも必ずぶつかる壁です。
私はブログ記事を毎日書いてますが、それでも、最初の1文字目が書けずにモヤモヤしてしまう日があります。
書けないのは“気持ち”が先に走っている証拠
ここで大事なのは、書けない自分を責めることではありません。
むしろ、「読者のことを真剣に考えてるからこそ、言葉を選びすぎてしまっている」
そういう“誠実な状態”だと受け止めてあげてください。
解決策は「書かないで、話す」
そんなとき、私が必ずやっているのがこの方法です。
書こうとせずに、まず“話す”
これは、本当に効果があります。
なぜ話すと書けるようになるのか?
人は、“話す”ときには思考が流れるように整理され、
“書く”ときには頭が止まりやすいという脳の仕組みがあります。
「書く=整った形で出さなきゃ」
「話す=とりあえず言葉にすればいい」
だから、書けないときはまず「話すことで頭をほぐす」のです。
実際のやり方(私が使ってる方法)
STEP1:スマホのボイスメモを開く
→ iPhoneの「ボイスメモ」やLINEの音声録音でもOKです
STEP2:「誰かに話すつもり」でテーマを語る
例:「今回、なんでこのテーマにしたのか?」
「誰に向けて書いてるのか?」
「何を一番伝えたいのか?」
※ポイントは「書くつもりで話さないこと」
あくまで自然に「おしゃべり」すること。
STEP3:録音した内容を聞き返しながらメモする
ここでやっと「書く」フェーズです。
録音の中から「これは使えそう」という表現をピックアップして、
構成に沿って流し込んでいく。
STEP4:話し言葉→書き言葉に変換
たとえば、「だからさ〜」みたいな口語は、
「そのためには」に変えれば文章として成立します。
ポイントは、“全部書き言葉に直そうとしないこと”
少しだけ“話し言葉のリズム”を残すと、読みやすく、親しみが出ます。
この方法が効果的な理由(3つ)です。
| 理由 | 説明 |
|---|---|
| ①「思考の流れ」が見える | 話すと、自分が自然に何を重要視しているかが浮き彫りになる |
| ②「感情」が入っている | 書くと感情が削がれやすいが、話すと“熱”が伝わる |
| ③「ネタ切れ防止」にもなる | 話してみると、「あ、これも書こうかな」と連想が広がる |
加えて伝えたいのは、「書けない=ダメ」じゃないということです。
むしろ、あなたが「ちゃんと届けたい」と思っている証拠。
その気持ちがあるなら、必ず書けるようになります。
だから、手が止まったら、
「よし、今は“話す時間”なんだな」
こう割り切って、出力方法を変えてみましょう。
この切り替えだけで、だいぶ楽になります。
第7章:コンテンツ制作でよくある誤解とつまずきポイント
書いたのに、読まれない…なぜ?
「リサーチもした」
「構成も意識した」
「伝えたいことも明確にした」
なのに…
「全然読まれない」
「スキが付かない」
「反応ゼロ」
これも、実はすごくよくある現象です。
そして、これは“文章のうまさ”や“テクニックの不足”が原因じゃないことが多いのです。
実は…誤解されてるコンテンツ制作の常識
初心者さんに多いのが、「コンテンツの正解」に対する“思い込み”です。
その思い込みが、かえって読み手の心を遠ざけてしまう原因になっています。
ここでは、よくある誤解とその対処法をセットで紹介します。
誤解①:情報を“たくさん”詰め込めば価値が出る
「読者のために、できるだけ多くの情報を盛り込もう!」
→ これは逆効果になりがちです。
正解は「1つのメッセージ」に絞る方が伝わるということです。
情報が多すぎると、読者は「結局何が言いたいの?」と混乱します。
読者の満足度は「知識量」ではなく「納得感」で決まります。
誤解②:全部テンプレに沿えば正解
「とりあえず構成テンプレに当てはめて書けばいいんでしょ?」
もちろんテンプレートは便利ですが、読み手は“感情”で動きます。
テンプレだけでは、“あなたの視点”や“体験談”が抜け落ちがちです。
たとえば、
-
なぜこのテーマにしたのか
-
あなた自身の失敗談
-
それを伝えることで、相手がどうなるのか
こうした「温度」のある言葉が入ると、読者の心に届きます。
誤解③:1回で完璧な文章を書こうとする
「最初からしっかりした文章に仕上げよう」
そう思って書き始めちゃう方も中にはいますが
完璧主義こそ、手を止める最大の敵になります。
そういうときは
「下書きは雑でもいい」から始める、と割り切って
-
とりあえず話す
-
とりあえず箇条書きで出す
-
若干ブレてても最初は気にしない
こういう心がけも必要です。
まずは“形にする”ことです。
あとから“整える”ことは、いくらでもできるからです。
よくある“つまずきポイント”をまとめておきました↓
| つまずきポイント | 原因 | 解決策 |
|---|---|---|
| 何から書けばいいか分からない | テーマが大きすぎる or メッセージがぼやけてる | 「誰に、何を、なぜ」だけ決めて1行にまとめる |
| 手が止まる | 書きながら構成や表現を考えてしまっている | まずは「話す」→「書く」の順に切り替える |
| 書いたけど反応がない | 読者目線では「読むメリット」が見えない | 「あなたがこれを読むとこう変わります」と価値づけを追加する |
| 書く時間が足りない or 優先できない | 完璧を目指すあまり、気持ちが重くなっている | 「10分だけ録音→書き起こし」など“軽い一歩”で習慣にする |
「読まれない」のは実力のせいではない
反応がないと、「私の文章が下手だからかな」と落ち込みがちですが、
ほとんどの場合、それは“文章の設計”か“届け方”に問題があるだけです。
-
ターゲットが明確か
-
最初に全体像を見せているか
-
情報を絞れているか
-
読者が「自分ごと」と思える工夫があるか
このあたりをチェックするだけで、
コンテンツの伝わり方がまるで変わります。
次はいよいよコンテンツで“買ってよかった”と言われるために必要なことを解説します。
-
読者に本当に感謝されるコンテンツとは?
-
「買ってよかった!」を生む文章の秘密
-
信頼を築く最終の一手
などを説明していきますね。
第8章:コンテンツで“買ってよかった”と言われるために必要なこと
情報だけじゃ、人は動かない
ここまで読んでくださったあなたなら、
リサーチ → 構成 → 書き方 → ステップ分解 → 価値づけ
という“伝える技術”をしっかり学んできました。
でも最後にひとつだけ、絶対に伝えておきたいことがあります。
それは…
「人が感動して、信頼して、行動するのは、情報“だけ”じゃない」
ということです。
本当に買ってよかった!と言われるコンテンツとは?
それはズバリ、
「読んだあとに、心が軽くなる」コンテンツです。
情報があっても、心が動かなければ意味がない
-
正しいけど冷たい
-
詳しいけど疲れる
-
丁寧だけど刺さらない
これ、すべて“人としての温度”が足りない文章の特徴です。
「文章の奥に人を感じる」からこそ、信頼される
読者は、文章を読んで「なるほど」と思ったあと、
その奥にある“人柄”や“在り方”を無意識に感じ取っています。
そしてこう思います。
「この人から学びたい」
「この人の言葉は信じられる」
「この人がやってること、買ってみようかな」
これが、“買ってよかった”の本質です。
なので、コンテンツを書くときは
「温度のある文章」をつくるための3つの視点
を意識しながら書くといいです。
| 視点 | 具体的な書き方のヒント |
|---|---|
| ① なぜ書くのか? | 「このテーマをなぜ自分が伝えたいのか?」を書いてから始めると、使命感が滲み出る |
| ② だれのためか? | 「昔の自分」「あのときのクライアント」など、具体的な“顔の見える誰か”を想像して書く |
| ③ どう変わるか? | 「この文章を読んだら、相手の未来がどうよくなるか?」を常に意識しながら文末を設計する |
煽る・強い言葉・刺激的なタイトルなどは必要ありません。
たしかに一時的に注目される手法ですが、それらは信頼や満足にはつながらないからです。
一方で、
-
穏やかで
-
丁寧で
-
自分の言葉で話している
そんな文章は、長期的に読み続けられ、「また読みたい」「またこの人から買いたい」につながります。
読者がコンテンツを買うときって、心の中でこんなジャッジをしています。
「この人、信用できる?」
「この情報、本当に私に合ってる?」
このジャッジを乗り越えるために必要なのが、“信頼残高”です。
信頼残高を貯めるには?このようなことが必要です↓
| 方法 | 説明 |
|---|---|
| 一貫性のある主張 | 記事の中で主張がブレない、矛盾しない |
| 読者目線の丁寧な導線設計 | 「なぜ?」→「どうやって?」→「こう変われる」の流れが丁寧に作られている |
| 自分の弱さや失敗も見せる | 「この人も昔はできなかったんだ」と親近感を持たせる |
| 無理に売らない | 押し売り感ゼロで、「読み手の判断に任せる」姿勢 |
情報はググれば出てきます。
でも、「あなたにしか書けない文章」「あなたにしか書けない文章」は、あなただけの経験・想い・視点からしか生まれません。
たった一人にでも、「救われた」「気づけた」と思ってもらえたなら、
それはもう、“立派な価値”になります。
最後に
コンテンツを書くのって、ほんとうに勇気がいります。
言葉を選び、時間をかけて、誰かに届くか分からないまま発信しなきゃいけません。
でも、その勇気は、確実に誰かの人生を変えます。
「伝えたい」と思ったとき、
すでにあなたには“届ける資格”がありますし
だからこそ、自信を持って書いていってくださいね。
著者プロフィール:ねここ
在宅ワーカー歴4年。
月収0円から副業スタートし、現在はコンテンツ販売×ステップ配信で仕組み収益を確立。(noteも執筆中!)
未経験から1年でコンテンツ販売を教える側になった元薬剤師
ブログ/Instagram/X/スレッズ/YouTube/メルマガ/noteを使った
資産コンテンツ積み上げ術を日々共有中。
「半径1mの幸福の永続化」を目標にネットビジネスを始め2年で起業。
在宅ワークで生きられるための知識を毎日発信中。
ここまで読んでくれて
感謝だにゃ〜!
記事でお会いしましょう!
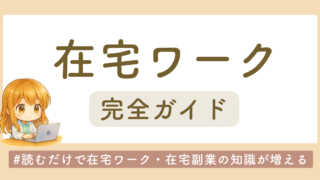
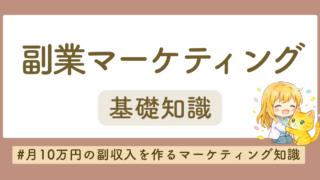
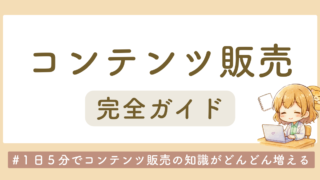
👉 ねここのリアルタイム不定期配信メルマガもあります!
https://nekoko89314.com/p/r/gTovjPDb
もっと学びたいあなたに
ここまで読んでくださったあなたへ。
きっと今、こう思っているのではないでしょうか。
「やってみたい。でも…本当に私にできるのかな」
「ここまでは理解できたけど、実際に書くとなるとやっぱり不安…」
大丈夫です。
“伝える力”は、センスではなく技術です。
そしてその技術は、
今回ご紹介したように「順番」に沿って進めれば、誰でも習得できるようになります。
でも
「このテーマで合ってる?」
「書いた文章、本当に読まれるかな?」
「もっと具体的なアドバイスが欲しい…」
もし、そんな気持ちが少しでもあるなら、
私がお届けしているメール講座もぜひ一度のぞいてみてください。
この講座では、こんなことが学べます
-
リサーチから執筆までの手順
-
伝わる構成の作り方
-
あなたのコンテンツを“商品になる”レベルまで引き上げる実践法
こんな方にこそ、届けたい
-
書き方を学んでも、実際に手が止まってしまう方
-
頑張っても反応が得られず、迷っている方
-
自分の経験や言葉を“ちゃんと価値として届けたい”と思っている方
あなたの言葉には、きっと誰かの人生を変える力があります。
あとは「伝え方」を少し学ぶだけなので
「ちゃんと伝わる文章」を買いて、自分の商品を作って販売していきたい方は、ぜひ受け取ってくださいね。
👉こちらから受け取れます
(今なら豪華特典付き)
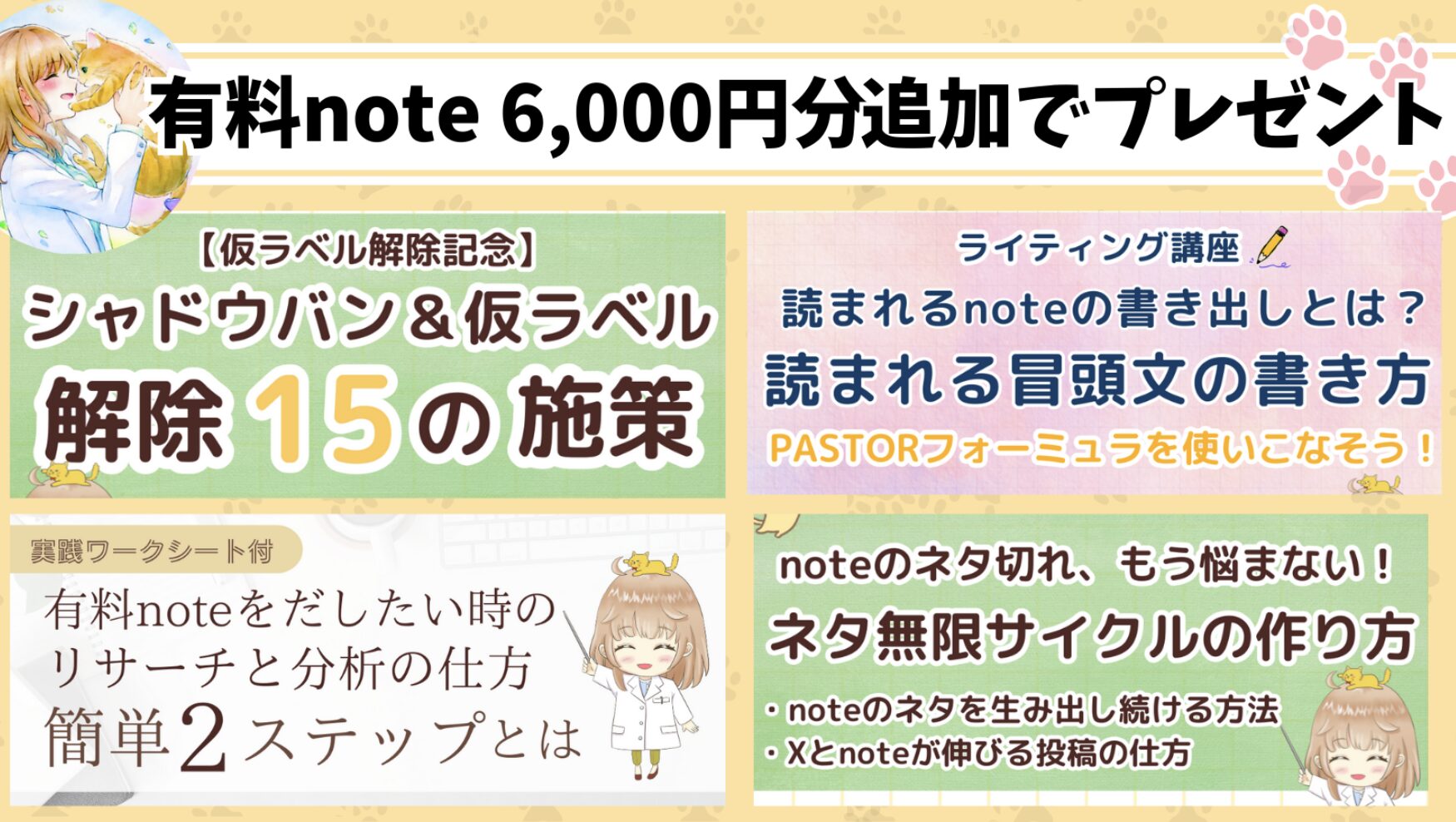
ぜひ、あなたもコンテンツ販売ライフをスタートしていきましょう。