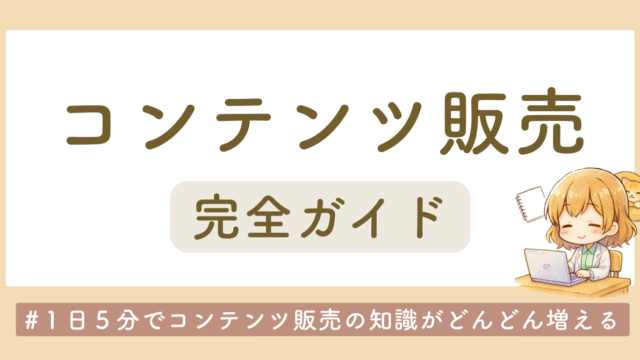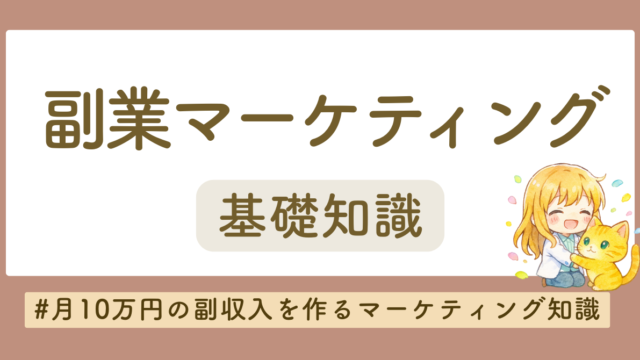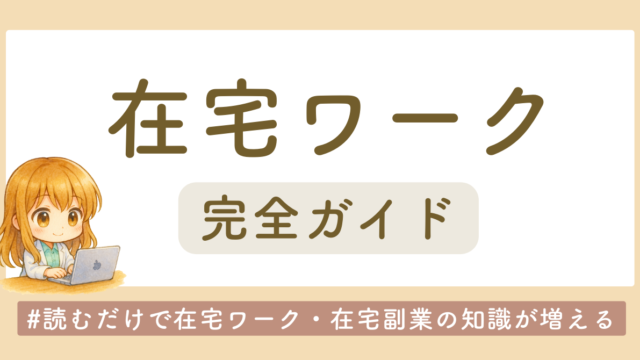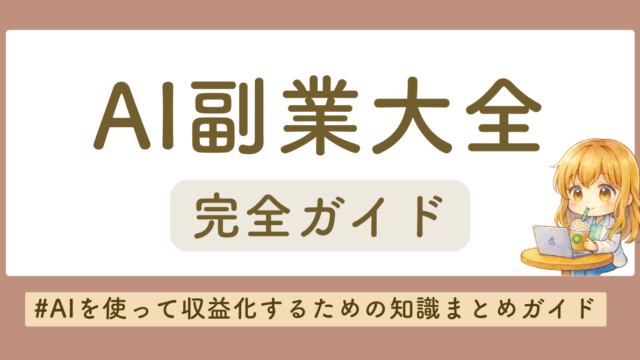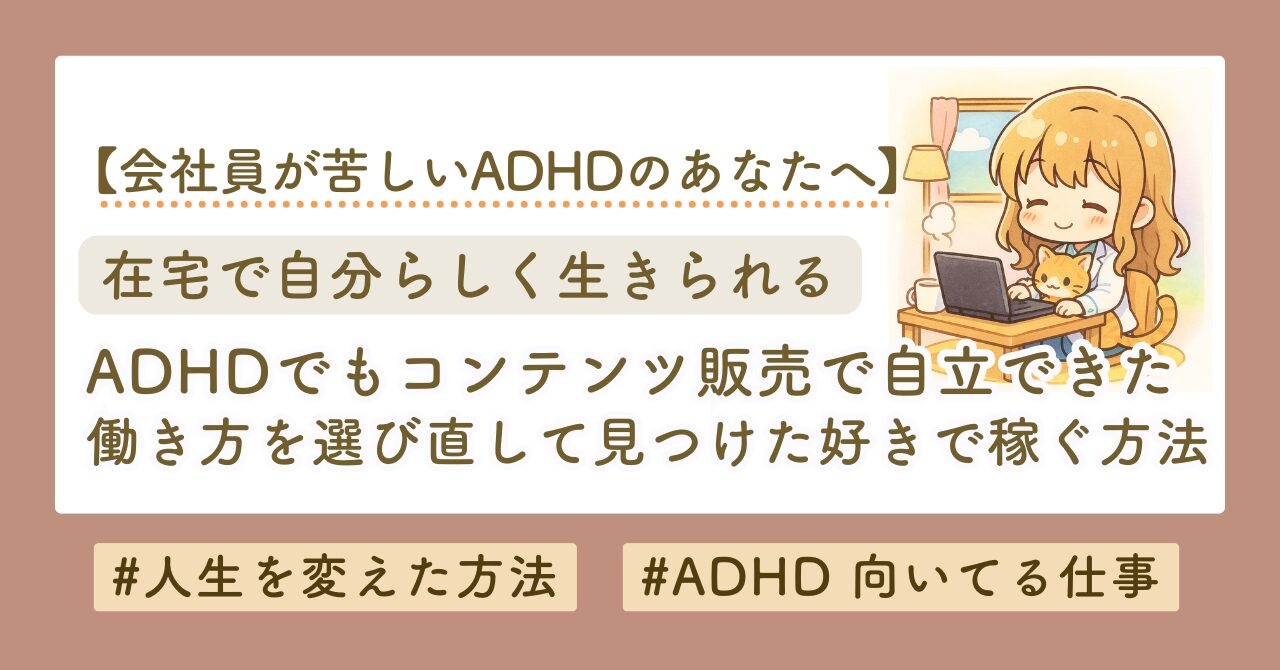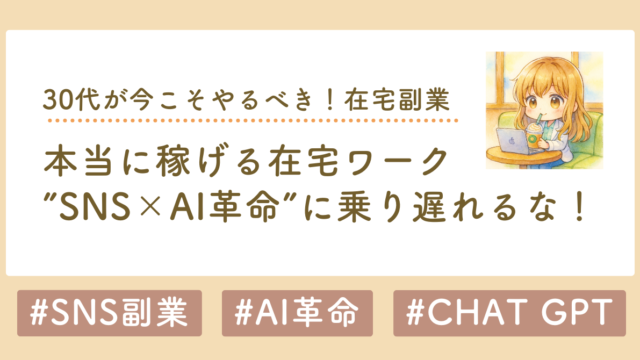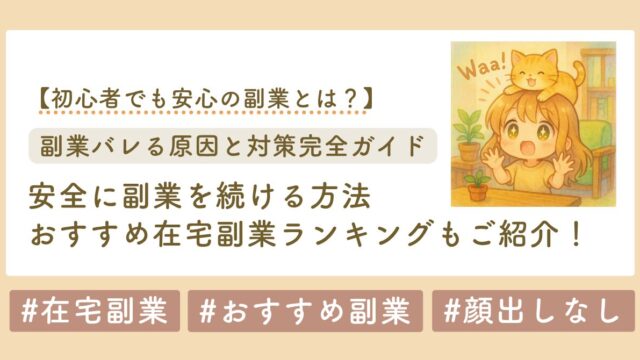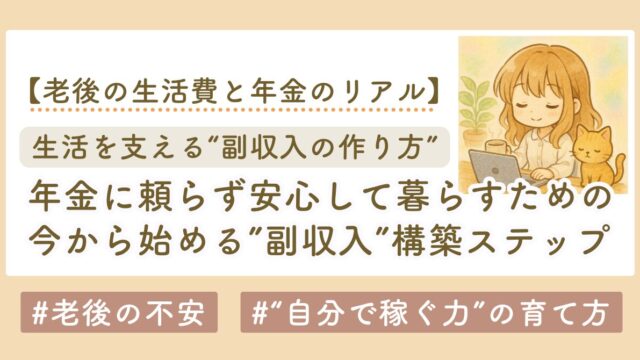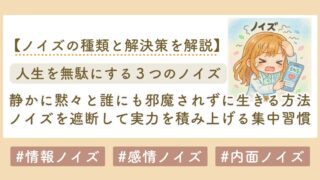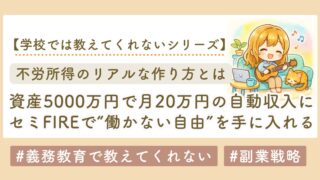はじめに:ADHDの私が人生を変えた方法
「ADHDの自分に合った働き方がわからない」
「頑張っても仕事が続かない。周りと同じように働くのがつらい」
「好きなことで生きていけたらいいのに…」
かつての私も、そう思いながら毎日を過ごしていました。
職場ではミスを連発し、人間関係にも疲れて、自己肯定感はどん底。
「普通に働くこと」が、これほどまでに苦しいとは思ってもいませんでした。
そんな私が、ある時ふとしたきっかけで出会ったのが、
「在宅ワーク」や「コンテンツ販売」といった、自分のペースでできる働き方でした。
最初は半信半疑で「自分には無理」「売るものなんてない」と思っていました。
でも、試行錯誤を重ねる中で少しずつ気づいたんです。
ADHDの脳は、“好きなこと”にしか反応しないけれど、
その好きなことには、誰よりも深く集中できる強みがある。
つまり、自分の特性に合った働き方を選べば、
苦しさではなく「才能」として活かすことができる
そう気づいた瞬間から、人生が変わり始めました。
この記事では、ADHDの私がどのようにして働き方を選び直し、
在宅ワーク・コンテンツ販売というスタイルで、自分らしく働く道を見つけたのかを具体的に解説していきます。
同じように「働き方に悩んでいる」「ADHDで自己否定を感じている」という方にこそ読んでいただきたい内容です。
第1章:ADHDの特性は、ただの“欠点”じゃない
こんにちは、ねここです。
この記事にたどり着いたあなたは、きっとこんな悩みや違和感を抱えているのではないでしょうか?
毎日同じ作業の繰り返しが若干、苦痛
集中力が続かず、つい仕事を先延ばしにしてしまう
やりたいことはあるのに、気分にムラがあって続けられない
人間関係や会社のルールに、なんとなく息苦しさを感じる
「私、どこか人と違うのかな?」という漠然とした不安がある
それ、もしかしたら「ADHDの気質」が関係しているかもしれません。
私自身も、まさに同じような悩みを抱えていました。
会社員時代は、時間通りに出勤し、決められた業務を黙々とこなす毎日に、どうしてもストレスを感じて順応できませんでした。
やるべきことは頭では分かっているのに、手が動かない。
締め切りギリギリになってからようやくスイッチが入る。
職場の人間関係にも過敏に反応してしまい、いつも疲れ果てていました。
そんなある日、ネットで「大人のADHD」という言葉を見かけたのです。
そこには、私とそっくりの思考や行動の特徴が書かれていました。
ADHD脳は“スポーツカー”みたいなもの
ADHDとは「注意欠如・多動症」と呼ばれますが、それは病気ではありません。
脳の特性であり、言ってみれば「操作方法の違うOSを積んだ脳」なんです。
興味のないことには集中できないけれど、逆に好きなことには異常なほど没頭できる
忘れっぽいけれど、ひらめきは抜群
計画通りに動くのは苦手だけど、行き当たりばったりの瞬発力がある
こうした特性を持つ脳は、言い換えれば「スポーツカー型の脳」です。
アクセルを踏み込めば、一気にトップスピードへ(過集中)
でも燃費が悪い(集中力が長く続かない)
ブレーキの利きが弱く、衝動的に行動してしまうこともある
スポーツカーは、普通の道路をノロノロ走るのは苦手です。
けれど、正しいコースで正しいアクセルの踏み方をすれば、誰よりも早くゴールに到達できる車です。
つまり、ADHDの特性を“どう活かすか”、どんな環境で働くかが重要なのです。
環境によって「才能」にも「短所」にも変わる
私たちADHD傾向のある人間にとって、環境の影響は非常に大きいです。
たとえば…
-
会社員として、毎日定時に出社してルーチン業務を繰り返す
→「サボっている」「空気が読めない」と思われやすい -
在宅ワークで、自分の得意ジャンルに集中して仕事をする
→「独創的」「スピードが早い」「アイデアが面白い」と評価される
つまり、短所に見える特性が、環境によって「才能」に変わるのです。
働き方を“選び直した”ことで私の人生は変わった
私がようやく「生きやすさ」を手にしたのは、
自分の特性を受け入れ、「自分に合う働き方を選び直した」からでした。
選び直した働き方とは…
「在宅ワーク」と「コンテンツ販売」です。
この働き方に変えた途端、生活はガラリと変わりました。
-
朝の満員電車に乗らなくていい
-
好きな時間に働ける
-
興味があるテーマに全力で取り組める
-
人間関係のストレスがない
-
自分のペースを守れる
ADHDという特性を責めるのではなく、活かすことにシフトしたことで、
本当に「自分のペースで」働けるようになったのです。
このブログでお伝えしたいこと
このブログでは、同じような悩みを抱えている方に向けて、
私の経験と知識をもとに、以下の内容をお届けしていきます。
-
ADHDの特性と向き合う方法
-
ADHDに向いている働き方/向いていない働き方の違い
-
在宅ワーク・コンテンツ販売がADHDに合っている理由
-
初心者でも始めやすい第一歩
-
継続するための工夫や仕組み化のコツ
-
自信を失わないマインドセット
「自分に合った働き方」は必ず存在する
ADHDを持っていると、
人と違うことがコンプレックスに感じるかもしれません。
でも私は声を大にして言いたいのです。
あなたの特性は「仕事になる」し、「価値」になる
合わない仕事を無理に頑張る必要はない
あなたの力が最大限に発揮される場所は、ちゃんと存在しています
私がそうだったように、あなたにも“合う働き方”がきっと見つかります。
読み進め方と次章について
記事は章ごとに構成しており、どこから読んでも分かりやすいように工夫しています。
でもまずは、次の【第2章】
「ADHDが苦手な仕事/得意な仕事」を読んでみてください。
自分に合う働き方のヒントが、必ず見つかるはずです。
第2章:ADHDが苦手な仕事、得意な仕事とは?【比較表付きで徹底解説】
ADHDと「仕事の向き不向き」の関係
ADHDという特性を持っていると、
働くうえで「なんとなくやりづらい」「ミスを繰り返す」といった経験をしたことがある方も多いと思います。
ただ、これは「あなたが能力不足だから」ではありません。
結論から言うと
ADHDは“向いていない仕事”では力が発揮できず、逆に“向いている仕事”だと驚くほど成果が出るのです。
これは私自身が実感したことでもあります。
会社員時代、私は
-
定時に出社して、
-
決まった手順で事務処理をして、
-
上司の指示通りに動き、
-
同僚と協力しながら案件を進める…
といった「普通の働き方」がどうしても続けられませんでした。
でも、フリーランスになってからは
-
ひとりで自由に仕事の内容を決められて、
-
興味があるテーマにだけ没頭できて、
-
文章や発信で誰かの役に立てる
という環境に切り替えたことで、
集中力も作業量も何倍にもなりました。
このように、ADHDの特性を知ったうえで仕事を選べば、
ストレスを減らしながら、自分らしく成果を出すことが可能になります。
ADHDに「向いていない仕事」の共通点とは?
ADHDの人にとって苦手になりやすい仕事には、ある共通点があります。
それは…
-
ルールや手順が厳格に決まっている
-
単調な作業が多い
-
ミスが許されない緊張感がある
-
人間関係が密接すぎる
-
マルチタスクが求められる
といった要素です。
これらは一見「誰にとっても面倒なこと」に見えるかもしれません。
でもADHDの人にとっては、これが集中力や意欲を根本から削ぐ要因になってしまうのです。
ADHDに向いていない仕事例【一覧表】
ADHDに向いていない仕事と言われてるものには、以下のようなものがあります。
| 職種 | なぜ向いていないか(ADHDの特性との相性) |
|---|---|
| 一般事務 | 単調な作業の繰り返し。ミスが許されず、集中力の維持が必要。 |
| 工場のライン作業 | 長時間のルーチンワークで刺激が少ない。感覚的に苦痛になりやすい。 |
| 接客・販売業 | 人間関係の調整や顧客対応などでストレスが多く、臨機応変さを求められる。 |
| 医療・介護などの対人職 | 感情コントロールとマルチタスクが常に求められる。疲弊しやすい。 |
| 管理職・プロジェクトマネジメント | 複数業務の管理やスケジュール調整が必須。ワーキングメモリに負担大。 |
もちろん、ADHDでもこういった職種で活躍している方はいます。
ですが、努力や訓練でなんとか適応しているケースが多く、継続的なエネルギー消耗を伴いやすいという傾向があります。
ADHDに「向いている仕事」の共通点とは?
一方で、ADHDの特性がプラスに働く仕事には、以下のような特徴があります。
-
興味を持ったテーマに深く集中できる余地がある
-
自由な発想・発信が求められる
-
成果主義で評価される
-
ひとりで完結する作業が多い
-
時間・空間の自由度が高い
これらの条件に当てはまる仕事は、
「ADHDの強み=好奇心・過集中・アイデア力」を存分に活かすことができます。
ADHDに向いている仕事例を挙げてみます。
| 職種 | なぜ向いているか(ADHDの特性との相性) |
|---|---|
| ブロガー・ライター | 一人で黙々と書ける。興味あるテーマに深く入れる。 |
| デザイナー・イラストレーター | 自由な発想と感性を活かせる。納期さえ守れば進め方は自由。 |
| 動画編集者 | クリエイティブで感覚的な作業が多い。ひとりで集中しやすい。 |
| コンテンツ販売 | 自分の経験や得意を商品化。好きな分野に特化して自由に売れる。 |
| 在宅ワーカー全般 | 時間・場所・作業内容すべてを自分で管理できる。 |
なぜ「在宅ワーク」と「コンテンツ販売」が特に相性が良いのか?
その中でも、特に在宅ワークやコンテンツ販売がADHDに向いている理由は、以下の3つです。
-
集中できるタイミングに合わせて仕事ができる
→ ADHDは「今やる気ある!」という瞬間が命。時間に縛られずに働けるのは強みです。 -
人間関係のストレスを最小化できる
→ 他人との摩擦が少ない分、自分の作業に集中できます。 -
興味のある分野で深掘りしやすい
→ 自分の「好き」や「経験」がそのまま商品になるので、没入しやすい。
ADHDに向いている仕事・向いていない仕事の違い
少しイメージしやすくするために、例え話をしてみましょう。
ADHDの人が「向いていない仕事」で働くというのは、
“水中で火を起こそうとする”ようなものです。
どんなに努力しても、そもそも環境が合っていないので、火はうまく燃えません。
やがて疲れ、諦め、自信を失ってしまいます…。
一方、「向いている仕事」で働くのは、
“乾いた薪と風が吹く場所で火をつける”ようなものです。
最初は小さな火でも、条件がそろえば一気に燃え上がり、
暖かく、力強く、周りに影響を与える炎になります。
この章のまとめをかいてみました。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 向いていない仕事 | ルーチン中心・マルチタスク・他人依存の多い職種は苦手になりやすい |
| 向いている仕事 | 自由度が高く、ひとり完結型・クリエイティブ系・自分軸で進められる仕事は相性が良い |
| 特に相性の良い働き方 | コンテンツ販売・在宅ワークは時間や場所の制限がなく、興味のある分野に集中できる |
| 自己責めにしない | できない仕事があるのは当たり前。環境と特性のミスマッチでしかない |
ここまで読んで、「なるほど、自分はこっちの仕事が合いそうかも」と少しイメージが湧いてきた方もいるかもしれません。
次の【第3章】では、
ADHDの特性がなぜ「コンテンツ販売」や「在宅ワーク」にマッチするのか、
より具体的な理由や実例、成功しやすい働き方の設計について詳しく掘り下げていきます。
第3章:なぜADHDには「コンテンツ販売」や「在宅ワーク」が向いているのか?
ADHDは「好きなこと」には圧倒的に強い
ADHDの特性の中でも、非常にユニークで強力なのが、「過集中(ハイパーフォーカス)」という状態です。
これは、興味のあることに対しては周囲の音も時間の感覚も忘れて、
まるで“ゾーン”に入ったように深く没頭できる状態のこと。
一見、ADHDは「集中力がない」と思われがちですが、実はその逆。
脳の構造上、“好きなことにしか脳が反応しない”というだけであり、
条件さえ整えば、誰よりも深く・長く・強く集中できるんです。
この特性が、在宅ワークやコンテンツ販売にはピッタリ当てはまります。
なぜ「在宅ワーク」や「コンテンツ販売」が相性抜群なのか?3つの理由
ADHDにとって、この2つの働き方が特に相性が良い理由を、以下にまとめます。
理由①:時間の自由度が高く「集中できる瞬間」に作業できるから
ADHDの人は、集中力に“波”があります。
朝はぼーっとしていて動けないけど、夜中に突然スイッチが入ったりする。
やる気が出るタイミングが決まっていないのは、特性によるものです。
会社員だと、やる気のない9時に出社して、
眠気と戦いながら17時まで耐える…なんてことになりますが、
在宅ワークやコンテンツ販売なら:
-
夜型でもOK
-
1日中やらなくても、1〜2時間の集中で成果が出せる
-
「やりたくなった時」だけ動けば良い
というように、自分のリズムで仕事ができるのです。
理由②:ひとりで作業できるから人間関係のストレスが激減する
ADHDの人は、対人関係で疲れやすい傾向があります。
特に、空気を読みすぎたり、場に合わせようとして無理をすることで、エネルギーを大量に消耗してしまうことも。
在宅ワークやコンテンツ販売は、基本的にひとり完結型の仕事です。
-
誰かに話しかけられて集中が切れることもない
-
社内の雑談や上司との報連絡に気を遣わなくていい
-
自分のペースでコツコツ進められる
こうした環境は、ADHDの人にとって非常に快適です。
理由③:自分の「好き」や「得意」がそのまま“商品”になるから
コンテンツ販売は、自分の経験・スキル・知識・視点を活かして
「情報」や「学び」を形にして売る働き方です。
たとえば:
-
過去に自分が悩んでいたこと
-
そこからどうやって乗り越えたか
-
それを文章やPDF、音声や動画にまとめて販売する
というイメージです。
ADHDの人が得意なことって、たとえば以下のようなことがあります:
好きなことを徹底的に調べる
人とは違う視点や着眼点を持っている
自分の体験に対して感受性が高い
アイデアが豊富で、企画力に優れている
これらを“コンテンツ”という形でアウトプットすれば、
自然とファンが付き、売上が立つようになります。
ADHDにとって、コンテンツ販売は“最適な表現の場”
会社では「周りと同じようにやること」が求められます。
でも、コンテンツ販売の世界では逆です。
他人と違う視点
自分なりの表現
独自の価値観
これらが“差別化”として武器になります。
たとえば、ADHDの当事者として
ADHDの生きづらさ
克服のプロセス
自分に合う働き方の模索
をリアルに語ったコンテンツがあれば、
同じ悩みを持つ人にとって「ものすごく価値のある情報」になります。
つまり、「人と違う」が価値になる場所なんです。
ADHDの特性 × コンテンツ販売の相性を図で見てみますね。
| ADHDの特性 | コンテンツ販売で活かせるポイント |
|---|---|
| 興味のあることへの過集中 | 好きなテーマを掘り下げて情報に変える |
| 衝動性(思いつき行動) | 発信や商品づくりのスピード感に活かせる |
| 感受性が強い | 読者に刺さる言葉を生み出せる。共感力が強みになる |
| 忘れっぽさ | 自分の経験を「記録」に変えることで価値になる |
| 自己肯定感の低下傾向 | 自分の実体験を振り返り、同じ悩みの人の助けになることで自信がつく |
コンテンツ販売は「話したいことを、誰かのために変換する」仕事
ADHDの人って、得意な話題になると止まらなくなることありませんか?
自分の好きなことになると、語りたい気持ちがあふれてきますよね。
実は、コンテンツ販売って「その“話したいこと”を、必要な人向けに編集して届ける」というだけなんです。
-
自分が経験してきた悩み
-
試行錯誤してきた工夫
-
他人に言ってもピンとこなかった気付き
これらを、言葉にして、PDFやnote、動画にして届けるだけ。
つまり、「誰かの悩みに寄り添いながら、自分のことを語る」ことが仕事になる。
これって、ADHDの人にとって、かなり自然なスタイルじゃないでしょうか?
この章のまとめ
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| ADHDは「集中力がない」のではなく「選んで集中する」脳 | 興味あるテーマでは最強。在宅やコンテンツ販売ならそれを活かせる |
| 在宅ワークの自由度が“波のある集中力”とマッチ | 朝じゃなくても、夜でも、自分のタイミングで働ける |
| 人間関係が最小限なので疲れにくい | 社内調整や雑談に気を使わずに済む環境 |
| コンテンツ販売は“好き・経験・視点”が商品になる | 自分の言葉がそのまま価値になり、人の役に立てる働き方 |
| 「自分にしかないもの」で勝負できる | 人と違ってOKな世界。むしろ“違い”が強みになるのが最大の魅力 |
ここまでで、
なぜADHDの人にとって「コンテンツ販売」や「在宅ワーク」が最適なのかを説明してきました。
でも、読者の方の中には…
「でも、具体的にどうやって始めるの?」
「最初の一歩が怖い…」
「実際に商品を作るって、何をどうすればいいの?」
という疑問や不安があるかもしれません。
そこで次の【第4章】では、
ADHDの人が実際に“コンテンツ販売”を始めるためのステップと、つまずきやすいポイントの回避法を解説します。
「自分にもできるかも」と思えた方は、ぜひ続きを読んでみてくださいね!
第4章:ADHDの私が「コンテンツ販売」を始めるまでにやった5つのステップ
「何から始めたらいいか分からない」あなたへ
「コンテンツ販売って良さそうだけど、どうやって始めるの?」
「そもそも、自分には売るような知識も経験もない気がする…」
そう感じるのは、まったく自然なことです。
私自身も最初は、
-
noteって何?
-
自分の商品ってなに?
-
そもそも誰かが買ってくれるの?
と、疑問だらけでした。
でも、ADHDの私が“無理せず続けられる形”で、少しずつ積み上げてきたステップがあるので、今回はそれを具体的に紹介します。
ADHDの特性に合わせた「ゆるやかな5ステップ」
ADHDは「いきなり全部やる」のがとても苦手です。
完璧を求めすぎると、手が止まってしまいます。
だからこそ、このステップでは
情報を最小限にする
作業を小さく分ける
ゴールを近くに設定する
という工夫を取り入れています。
ステップ①:まず「売るため」じゃなく「話したいことリスト」を作る
いきなり「商品を作る」ではなく、まずは“自分が話したいテーマ”を思いつくまま書き出してみましょう。
たとえば…
-
昔、自分が悩んでいたこと
-
人よりハマったこと(趣味、沼)
-
気付いたら調べてしまうこと
-
周りに語りたくなること
-
よく友人から相談されること
こうした「誰にも頼まれてないけど、つい話したくなること」こそあなたにとっての“金の鉱脈”です。
これが後々、販売するコンテンツの種になります。
ステップ②:「過去の自分」に向けて書いてみる
書き出したリストの中から、「昔の自分が困っていたこと」をひとつ選んでみましょう。
そして、その悩みに対して今のあなたが
「こうしたらラクになったよ」「私はこう考えたよ」
と伝えるつもりで、文章を書いてみてください。
このときのポイントは、
-
うまく書こうとしない
-
正しい日本語でなくていい
-
誰かを感動させようとしない
「過去の自分を励ます手紙」のつもりで書くと、スルスル言葉が出てきます。
ステップ③:「無料記事」として公開して反応を見る
次に、noteやブログなどでその文章を無料公開してみましょう。
最初から有料商品にするのではなく、
-
気軽に書ける
-
誰でも読める
-
反応がもらえる
という意味で、「無料記事」はとてもおすすめです。
ADHDの人は「反応が見える」とモチベーションが上がりやすい傾向があるので、
「いいね」や「フォロー」などの小さな反応が“継続の燃料”になります。
ステップ④:「もっと詳しく知りたい人向け」にまとめ直す
無料で公開した記事に対して、
-
感想コメントが来た
-
もっと深く語りたくなった
-
そのテーマについて追加で書きたくなった
そんなときが、「コンテンツ化のタイミング」です。
ここではじめて、
PDFにまとめる
noteの有料記事にする
Canvaで簡単にデザインを整える
音声で喋って録音して売る
などの形で、「自分だけの商品」を作っていきます。
大事なのは、“ゼロから作ろうとしない”こと。
先に出した無料コンテンツを元に“組み立て直す”ことで、スムーズに進みます。
ステップ⑤:「これを知ってほしい人」に向けて発信する
商品ができたら、次は届ける段階です。
SNSが苦手な人は、無理して毎日投稿しなくても構いません。
でも、「こんな人に知ってほしい」という理想の読者を1人、明確にしておきましょう。
たとえば:
昔の私と同じように、働き方で悩んでいる人
ADHDの特性に振り回されてると感じている人
好きなことを仕事にしたいけど、自信が持てない人
この「1人の理想の読者」に向けて書けば、言葉がブレず、共感も得られやすくなります。
ADHDの人がつまずきやすいポイントとその対策がこちらです。
| つまずきポイント | 対策方法 |
|---|---|
| 完璧を求めすぎて進まない | 「50点で公開、あとで直す」でOK。とにかく出してみる。 |
| 情報収集ばかりで手が動かない | 「5分だけ書く」から始める。行動のハードルを限界まで下げる。 |
| 発信が怖い、批判されたくない | まずは「過去の自分に向けて書く」。他人を意識せず、自分の物語を書く。 |
| 途中で飽きてやめてしまう | 興味が続かないのは自然。「飽きたら別テーマで書けばいい」と割り切る。 |
| 商品を売るのが怖い | 無料で提供→反応を見る→そこから派生商品を作る、の流れで負担なく始める。 |
ADHDにやさしい「ゆる始め設計」がカギ
コンテンツ販売において、
ADHDの特性に合わせた“環境設計”が極めて重要です。
たとえば:
作業場所は「好きな音楽が聴ける静かなカフェ」
作業時間は「夜中の1時間だけ」
作業内容は「その日の気分で選べるリストを用意」
書けない日は「音声で話して録音」しておく
など、自分が気持ちよく動ける「勝ちパターン」を探すことが継続のカギになります。
ADHDの特性に合わせて、
「やる気の出る瞬間に、やれる方法で、やりたいことから始める」
これが、長く続けられて成果にもつながる方法です。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① | 「売る」より先に「語りたいことリスト」を作る |
| ② | 過去の自分に向けたメッセージを書く |
| ③ | 無料で公開して反応を見てみる |
| ④ | 反応や手応えをもとにコンテンツ商品化 |
| ⑤ | 理想の読者を1人決めて、丁寧に届ける |
ここまでで、
「自分にも始められるかも」「やってみたいテーマが見つかった」
そんな方も出てきているのではないでしょうか。
でも、ここから先には「続けられない問題」「収益にならない不安」など、
ADHDならではの“落とし穴”もあります。
そこで次の【第5章】では、
ADHDの人がコンテンツ販売を“継続して、収益化していく”ためのマインドと仕組みづくりについて、詳しく解説します。
第5章:ADHDの私がコンテンツ販売を“続けられた理由”と“収益につながった習慣”
始めるより「続けること」の方が何倍も難しかった
正直に言えば、コンテンツ販売を始めるよりも、続けることの方が圧倒的に難しかったです。
最初は勢いで記事を書ける。
でも数日経つと、ADHD特有の「飽き」や「刺激への慣れ」がやってきて、
-
書く気が出ない
-
ネタが思いつかない
-
SNSで他人と比べて落ち込む
-
買ってくれる人がいなくて不安になる
こんな感情が一気に押し寄せてきます。
私も例外ではなく、何度も手が止まりました。
でも、そこを乗り越えて続けられたのは、仕組みと考え方を変えたからです。
ADHDが続かないのは「意志の弱さ」ではなく「仕組み不足」
よく、「三日坊主=自分の根性が足りない」と思われがちですが、
ADHDにおいてはそれ、完全に誤解です。
ADHDの脳は「短期的な報酬」がないと行動が持続しづらく、
かつ「先の見通し」が立たないと不安が暴走して行動が止まります。
つまり、
意志ではなく、仕組みと刺激の与え方で継続はコントロールできるということです。
続けるために私が導入した5つの工夫
工夫①:「やる気が出ない日」を前提にカレンダーを設計する
ADHDの私は、毎日書き続けることはあまり得意ではありません。
でも、週に3〜4日は必ず“書きたい”日があります。
だから、「やる気の出ない日を前提」にスケジュールを設計しました。
例:
| 曜日 | 予定 |
|---|---|
| 月曜 | ネタ出し(気楽な作業) |
| 火曜 | 休む(無理して動かない) |
| 水曜 | 書く(集中できる日を選ぶ) |
| 木曜 | 推敲・校正 |
| 金曜 | 公開&ゆるくSNS発信 |
| 土日 | 完全休養か、新ネタの妄想時間 |
こうすると、「動ける日」に集中してアウトプットができるようになります。
工夫②:「ご褒美スイッチ」で短期報酬を用意する
ADHDの脳は「長期的な利益」より「今の快感」に敏感です。
だから私は、作業ごとに「ミニご褒美」を用意しました。
-
1000文字書いたら、お気に入りの紅茶を飲む
-
記事公開できたら、インスタを見る
-
1タスクおえたら、アプリで漫画を読んでOK
こうした「自分で自分に報酬を与える仕組み」が、行動のスイッチを押すきっかけになります。
工夫③:「一人で考えない」仕組みを持つ
ADHDの人は、頭の中でグルグル考え続けてしまうことが多いです。
そして考えすぎて疲れ、何もできなくなるのです。
だから私は、次のようなサポート構造を作りました。
-
ビジネス系のグループチャットに参加(刺激になる)
-
他人の発信を見てネタを思いつく場を作る(模倣OK)
-
メール講座の読者の声を保管しておく(やる気が落ちた時に読む)
つまり、「刺激をもらえる環境」+「応援の声に触れる習慣」が、継続の背中を押してくれたのです。
工夫④:成果を数値じゃなく「意味」で測る
ADHDの人は、「成果が出ないとやる気がゼロになる」ことが多いです。
私は最初の2か月、1円も稼げませんでした。
でもやめなかったのは、
-
「自分の言葉が誰かに届いた」
-
「前よりも文章が書けるようになった」
-
「苦手なSNSに1投稿できた」
などの“意味のある前進”に焦点を当てていたからです。
数値ではなく、成長や変化に気づく習慣が、モチベーションの源になります。
工夫⑤:「書かない日」も“収益につながる仕組み”を作る
ADHDの私は、波がある以上「毎日安定して動く」のは無理です。
だからこそ、「動けない日」でも売上が出るように、
自動化の仕組みを導入していきました。
たとえば:
-
記事の最後にメール講座を設置
-
自動で商品説明へつなげる
-
ブログからステップメールへ誘導
-
LINE登録者限定で特典を配布する
このような“自分が寝ていても動く仕組み”を持つことで、
エネルギーの波に左右されずにビジネスを続けられるようになります。
ADHDの継続には「戦略的な甘やかし」が必要
ADHDの人は、「根性論」で続けることができません。
集中できない日、落ち込む日、自信をなくす日は必ず来ます。
だからこそ、自分に対して
-
やさしくて
-
柔らかくて
-
戦略的に甘やかせる
そんな環境を設計することが、継続と収益化のカギになります。
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| ADHDは継続が苦手なわけじゃない | 合わない仕組みを使っているから続かないだけ |
| 継続には「予定」「ご褒美」「応援」が必要 | スケジュール設計・報酬設計・仲間づくりが継続の土台 |
| 成果を「意味」で捉える | 数字が出ない日も「成長」「変化」「行動」を評価ポイントにする |
| 自動化でエネルギー切れの日をカバー | メール講座・note導線など「寝てても収益が生まれる仕組み」を早めに持つこと |
| 戦略的な“甘やかし”がカギ | 自分のペース・感情の波を許容した仕組み設計で、無理なく継続できる |
ここまでで、
-
ADHDの特性を活かす働き方とは?
-
コンテンツ販売がなぜ合うのか?
-
どうやって始めて、どうやって続けるのか?
という全体像をつかんでいただけたと思います。
最後の【第6章】では、
「読者とのつながりを育てる」ためのメール講座設計と、そのメリットについて解説します。
ここが、コンテンツ販売を“単発”で終わらせず、
“長期的に収益が積み上がるビジネス”へと育てていく最大のポイントです。
第6章:ADHDの私が「メール講座」で人生を変えた理由と、その仕組みのつくり方
商品を“売り込まなくていい”働き方がしたかった
ADHDの私は、ずっと「売る」ことが苦手でした。
自分を売り込むのが怖い
商品を紹介するだけで罪悪感がある
セールス文章を書こうとすると、手が止まる
SNSで「買ってください!」と言うのがしんどい
そんな私が、初めて心地よく商品を紹介できたのが、メール講座(ステップメール)という仕組みでした。
この仕組みを取り入れたことで、
ガツガツ売り込まなくても
寝ている間にも
自分の世界観に共感してくれた人が
自然と商品を買ってくれる
という状態が作れたのです。
「メール講座」はADHDにとって最適な“営業アシスタント”
そもそもメール講座(ステップメール)とは何か?
簡単に言うと、
メルマガに登録してくれた人に対して、
あらかじめ設定した複数通のメールが、数日に分けて自動で届く仕組み
のことです。
そしてその中で、
あなたのストーリー
商品に込めた想い
商品が誰の役に立つか
実際の変化・成果
などを、段階的に伝えていきます。
すると、読み手は「納得」「共感」「理解」を経て、
自然な流れで購入に至るようになるのです。
つまり、メール講座は「売る」のではなく、
“必要な人が買いやすくなる状態”をつくるツールなんです。
ADHD的・メール講座を導入する3つのメリット
①:一度つくれば、ずっと“自動で仕事してくれる”
ADHDは、毎日同じことを繰り返すのがとにかく苦手です。
「毎回、売り込みの文章を書く」のはエネルギーを消耗しますよね。
でも、ステップメールは一度設定すれば、
-
新規フォロワーが来たとき
-
noteを読んで登録されたとき
-
ブログに流入があったとき
どんなタイミングでも、あなたの代わりに商品を紹介し続けてくれます。
②:「今は買わない人」に“関係性”を温めておける
ADHDの人は、「一発勝負」「すぐ結果を出せ」というプレッシャーが苦手です。
メール講座なら、
「今は買わないけど気になってる人」とも
関係性を維持できるのが大きなメリット。
1週間、2週間かけて信頼関係が構築され、
読み手のタイミングで購入してもらえるのです。
③:ADHDの“感情・思考の揺れ”も味方にできる
ADHDの人って、熱量が一気に上がったり、
突然アイデアが湧いたりしますよね?
ステップメールなら、その時の“過集中モード”で一気に書いておけばOK。
毎日SNSでコンディションを整えて発信する必要がありません。
ADHD的・ステップメールの中身の構成(5通構成の例)
以下は、ADHDの私が最初に組んだステップメールの一例です。
| 通数 | 内容 |
|---|---|
| 第1通 | 自己紹介と、「なぜこのメール講座を作ったのか」 |
| 第2通 | だめだった頃の私と、うまくいかなかった働き方 |
| 第3通 | 今の働き方(コンテンツ販売)との出会いと変化 |
| 第4通 | 実際に売れた初めての商品と、その感動体験 |
| 第5通 | 今回紹介する商品の内容と、どんな人に向いているか |
この構成をベースに、必要に応じて通数を増やしたり、
音声・PDF・動画などで補足すれば、
あなたらしい世界観がしっかり伝わるメール講座が完成します。
ADHDがメール講座でつまずきやすいポイントと対策も載せておきますね。
| つまずきポイント | 対策方法 |
|---|---|
| 何を書けばいいかわからない | 「過去の自分」に宛てて書く。実体験ベースなら書きやすい。 |
| 書く気分にならない | 過集中が来た日にまとめて書く。毎日書かなくてOK。 |
| 最初の文章が固くなりがち | 「友達にLINEで相談された」つもりで書くと自然な言葉になる。 |
| 商品紹介の文章で手が止まる | 「私はこれで助かった、だから共有したい」スタンスで書けば押し売りにならない。 |
やる気のある日に作っておけば、気分が落ちた日でもシステムが稼働し続け
事前に文章で要点を書き溜めておけば、売り込まずに自動で商品が売れるようになります。
これこそ、気分屋なADHDに必要な「自動売りのシステム」です。
最後に:あなたの“好き”と“特性”は、働き方を変える力になる
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
この記事では、ADHDという特性を持つ私が
会社という働き方に合わずに苦しんだこと
在宅ワークやコンテンツ販売という選択肢に出会ったことで希望が見えたこと
実際にどうやって始め、どうやって継続してきたか
ADHDならではの工夫と、自分を活かす仕組みづくり
を、具体的にお伝えしてきました。
もしかすると、あなたも今「普通の働き方ができない自分」に、
罪悪感や不安を抱えているかもしれません。
でも、それはあなたが「ダメ」なんじゃない。
ただ、使っているステージが違っていただけなんです。
ADHDは「集中力がない」のではなく、「合っていない場所で戦ってきた」だけ
私たちADHDの脳は、たしかに不器用な面があります。
でも、それと引き換えに、
驚くほどの過集中
圧倒的な感受性
他の人には見えない視点
という、強烈な“ギフト”も持ち合わせています。
この脳に合う働き方を見つけることで、
無理に「頑張る」のではなく、
自然体のまま才能を活かせるようになるのです。
ハリー・ポッターの“あの女優”も、ADHDだった
あなたも知っているでしょう、映画『ハリー・ポッター』シリーズでハーマイオニー役を演じたエマ・ワトソン。
実は彼女も、子どものころからADHDと診断され、集中力のなさに悩んでいたそうです。
勉強にも苦労し、自分を責める日々が続いていて。
でも、彼女はある時「完璧を目指すのをやめる」と決めたそうです。
そして代わりに、「自分が得意なことにエネルギーを注ぐ」と決めて、
演技や表現の世界に飛び込みました。
その結果、世界的な大女優になっただけでなく、
国連のスピーチで、何万人もの心を動かす影響力を持つ存在になりました。
あなたも“方向”さえ合えば、必ず光る
ADHDは「注意が散る脳」ではありません。
「好きなことにしか反応しない脳」です。
でもそれは裏を返せば、
“方向”さえ合えば、誰よりも深く集中できるということ。
それは、才能です。武器です。
ただの「苦手」ではなく、“使い方”さえ分かれば強みになるものなんです。
人生を変えるのは、根性ではなく「選び直し」
私は、ADHDを克服したわけではありません。
今でも忘れっぽいし、すぐ飽きるし、気分に左右されます。
でも、自分の特性を理解して、“環境”と“働き方”を選び直したことで、
無理せず、好きなことを続けられるようになりました。
このブログを通して伝えたかったのは、
「ADHDでも働ける」ではなく、
ADHDだからこそ選べる道があるということです。
人生を“選び直す”第一歩を
もし、ここまで読んで
-
「ADHDの自分でも何かできるかも」
-
「自分に合う働き方を探したい」
-
「無理せず売れる仕組みを持ちたい」
そう思ったなら、私が用意したメール講座にも登録してみてください。
この講座では、私が実際に
どうやって商品をつくり
どうやって届けて
どうやって無理せず収益を得たのか
を、具体的にお伝えしています。
コンテンツ販売 × 仕組み化 の無料メール講座はこちら
👇ねここの特別なメール講座ご登録はこちらから👇
静かな人こそ、世界を変える
これからは、静かに整え、集中して進める人が
確実に変化を起こしていく時代です。
あなたの中にある“静かな強さ”を、
どうかもう一度、信じてあげてください。
あなたのこれからの時間が、
ノイズのない、静かで豊かなものになりますように。
著者プロフィール:ねここ
在宅ワーカー歴4年。
月収0円から副業スタートし、現在はコンテンツ販売×ステップ配信で仕組み収益を確立。(noteも執筆中!)
未経験から1年でコンテンツ販売を教える側になった元薬剤師
ブログ/Instagram/X/スレッズ/YouTube/メルマガ/noteを使った
資産コンテンツ積み上げ術を日々共有中。
「半径1mの幸福の永続化」を目標にネットビジネスを始め2年で起業。
在宅ワークで生きられるための知識を毎日発信中。
ここまで読んでくれて
感謝だにゃ〜!
記事でお会いしましょう!
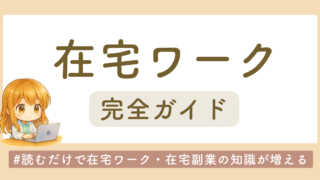
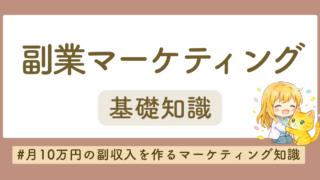
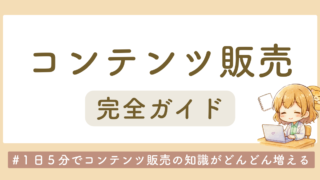
このブログが、あなたの新しい一歩のきっかけになりますように。