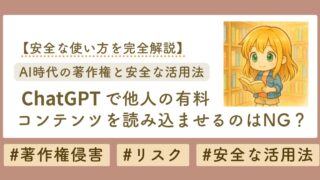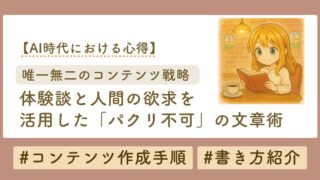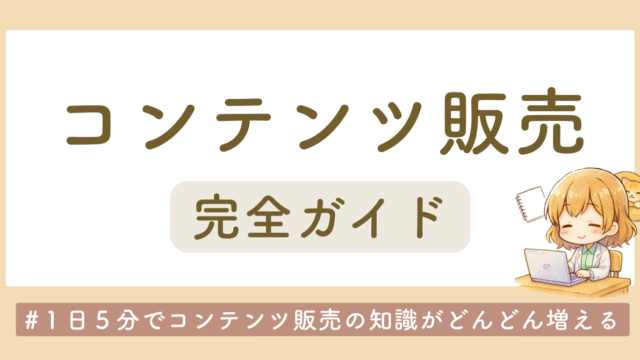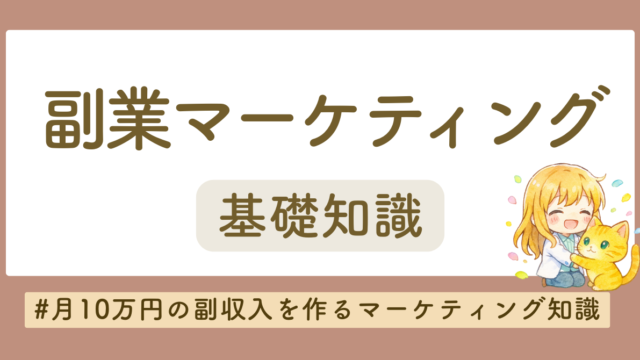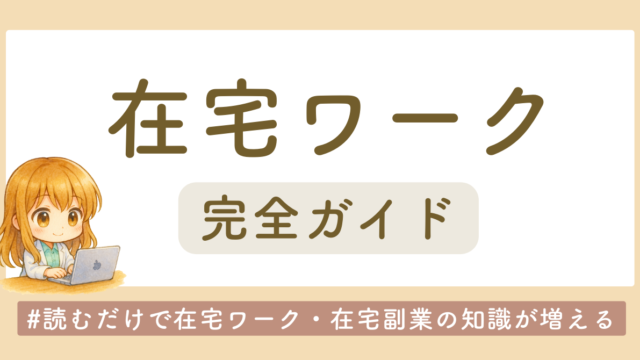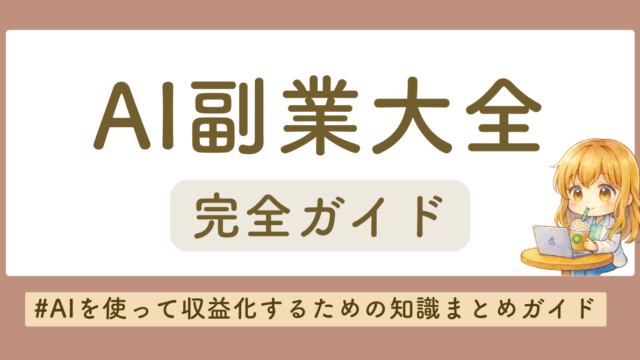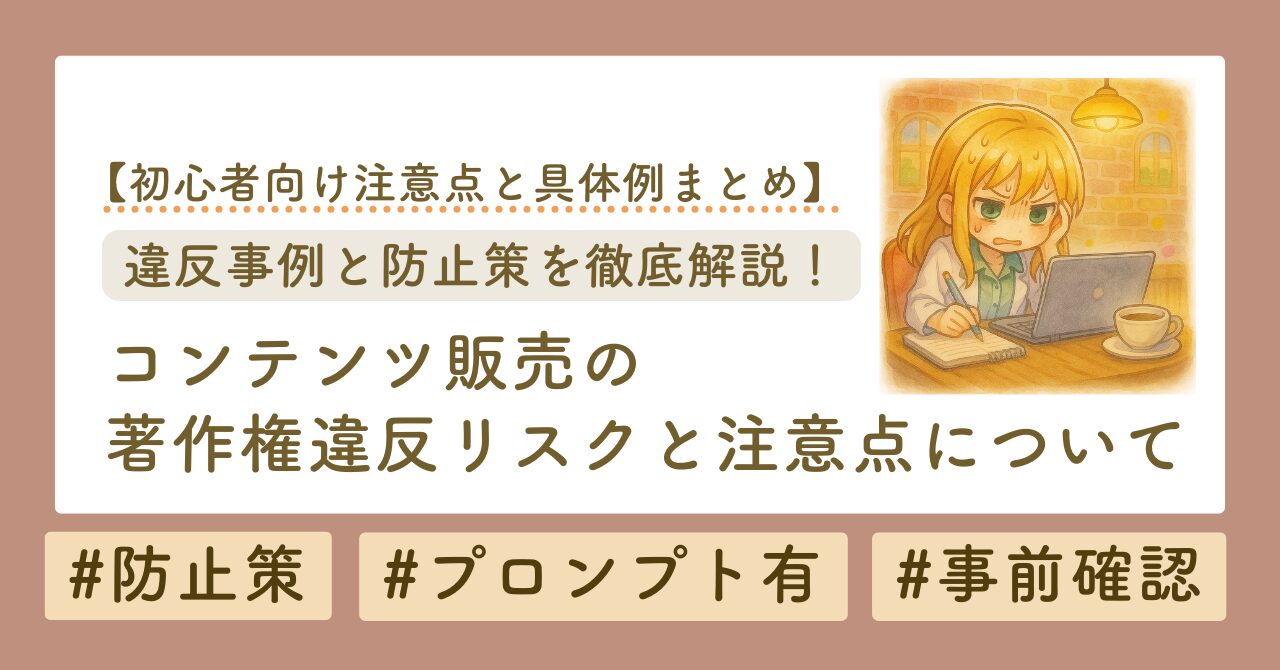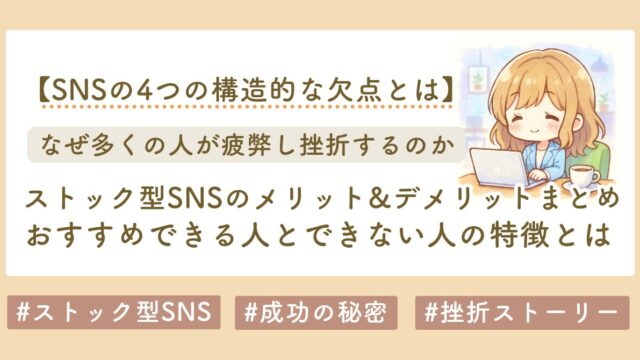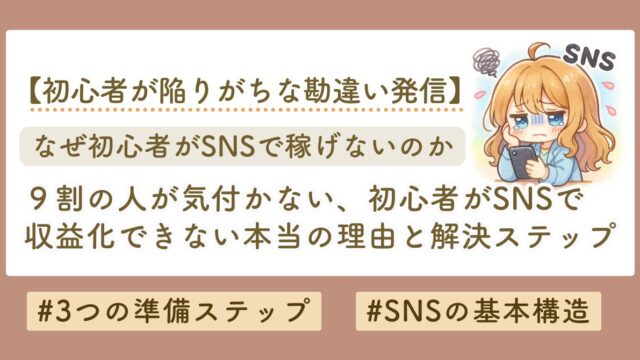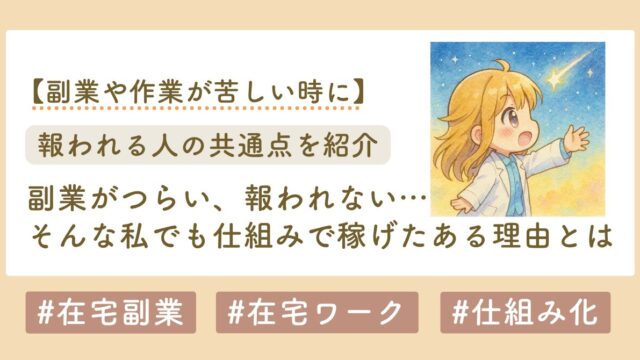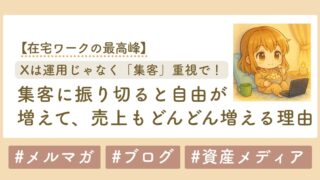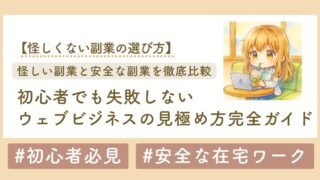私がコンテンツ販売に携わってきた中で多い相談が「著作権違反ってどこまでがOKで、どこからがNGなのか?」という問題です。
特に近年、オンライン教材やデジタルコンテンツ、電子書籍、note、Brainなど、個人がコンテンツを販売できるプラットフォームが増えたことにより、この疑問はさらに増大しています。
私自身もこのテーマについて学び直し、仲間やクライアントさんに注意事項も共有してきました。
今回は、その中で得たリアルな経験と法律的な知識を総動員して、コンテンツ販売における著作権違反の注意点を詳しく解説していきます。
著作権違反とは何か?
著作権違反(著作権侵害)とは、著作権者の許可なく、その著作物を使用することを指します。
ここで重要なのは、アイデア自体は保護されないということです。
例えば「ターゲット」といった単語は、マーケティングの世界でよく使われる言葉であり、これらを使っただけでは著作権違反にはなりません。
しかし、文章、画像、デザイン、プログラムなどの「表現」は保護されます。
つまり、同じアイデアを自分なりに表現することは問題ありませんが、表現自体のコピーがNGです。
コンテンツ販売でよくある著作権違反の具体例
ここでは、私が実際に見てきた典型的なケースを挙げながら説明します。
ブログやnoteの記事の丸写し
例えば、他人のnote記事を全文コピーして、自分のnoteに貼り付けて販売するケースです。
これは、依拠性(他人の記事を見ている)と類似性(表現が同じ)が満たされるため、完全にアウトです。
教材内容の無断使用
オンラインスクールで学んだ内容を、そのまま全文コピーして、自分の商品として売り出すパターンです。
これも記事を全文コピー→自分のものとして販売するケースなのでNGです。
Twitter・スレッドのコピー
あるインフルエンサーのスレッドを、ほぼ同じ言葉と構成で再投稿し、集客を図るパターンも非常に多いです。
これも明確な著作権侵害です。
引用と著作権侵害の違い
多くの方が混同するのが「引用」です。
引用は、著作権法で認められた行為ですが、以下の条件があります。
-
必ず出典を明示すること
-
自分の主張が主であり、引用部分は従
-
必要最小限の範囲であること
-
引用部分を改変しないこと
これらを満たしていれば、他人の文章を補足材料として利用できます。
しかし、「引用」と称して大量にコピーしたり、文章全体の大半を占めるような場合は認められません。
自分の言葉で語る重要性
著作権問題を根本的に解決する方法は、自分の言葉で語ることです。
以下のポイントを意識してください。
-
自分の体験談を加える
-
自分なりの例え話を使う
-
自分のオリジナルの視点を加える
これらを入れることで、
文章はあなた自身の表現となり、
著作権侵害のリスクを大幅に減らせます。
アイデアと表現の違いを理解する
ここが最も重要なポイントです。
「アイデア」は保護されず、「表現」が保護されるという点です。
「副業で月10万円稼ぐ」というアイデアは自由に使えますが、それをどう表現するかが著作権に関わります。
アイデアを自分の体験やストーリーと組み合わせることで、唯一無二のコンテンツになります。
OK例
「商品を売るときは、ターゲット設定とコンセプト設計が大事です。」
これはOK。完全に一般的なフレーズ。
NG例
「ターゲットを決めるときには、相手の1日のスケジュールをまるでストーカーのように追いかけ、どんなときに悩んで、どんなときに笑顔になるかを完全にイメージせよ。」
これを誰かの著作物から丸ごと持ってくるとNGです(依拠性・類似性でアウト)
よくある勘違い
❌ 「単語が被ったらパクリになる?」
→ 単語は大丈夫
❌ 「同じような構造やフレームワークを使ったらアウト?」
→ 構造やフレームワーク自体も基本的にはOK
ただし、説明文を
そっくりそのまま使うのがアウトです。
具体例① ブログ記事の無断コピー
📝 事例
例えば、ある有名な副業ブログで「5ステップで月10万円稼ぐ方法!」という記事があったとするよね。
あなたが「これすごくいいな〜!」と思って、その文章を丸ごとコピーして、自分のnoteに「5ステップで月10万円稼ぐ方法!」として投稿したとします。
❌ NGポイント
-
完全な文章のコピー(言い回し・例え話まで同じ)
-
自分の意見や補足なし
具体例② マーケティング教材の内容をそのまま商材化
📝 事例
誰かが作った「最新のインスタ運用ノウハウ」を、PDF教材として売っているとする。
あなたがそれを買って、「これは使える!」と、そのPDFの中身をほぼ丸写しして自分の名前で新しい商材として販売したら?
❌ NGポイント
-
教材は表現が保護対象(解説文、フレームワークの説明)
-
「自分の解釈を入れればOK」だと思っても、分量が少ないとアウト
-
売る=営利目的なので、違反の損害賠償が大きくなる
そのまま教材を売ってしまうとアウトになるので注意しよう。
マーケティング用語の使い方
マーケティング用語は自由に使えます。
ただし、その説明文や具体的表現を他人から丸ごと持ってきてはいけません。
例えば、「ターゲットは恋人のように一緒に過ごすイメージで考えましょう」という文章をそのままコピーするのはNGです。
自分なりに「私はターゲット設定を家族旅行の計画のように捉えています」と言い換えるなど、自分の視点を足すことで問題ありません。
SEO観点から見た著作権問題
SEOではオリジナリティが重視されます。
コピーコンテンツや重複コンテンツは、Googleの評価を大きく下げ、検索順位が圏外になるリスクがあります。
つまり、著作権を守ることは法的リスクを避けるだけでなく、SEO的にも有利です。
オリジナルコンテンツを積み上げることが、最終的に大きな資産になります。
コンテンツ販売で著作権を守るための具体的ステップ
ここで、実際に私が推奨するステップを紹介します。
-
リサーチ段階ではアイデアのみを集める
-
集めたアイデアを自分の言葉に書き換える
-
必ず自分の体験や事例を組み合わせる
-
自分が書いた文章を一晩寝かせて読み直す
-
不安ならAIツールやコピーチェックツールで確認する
-
出典が必要な場合は正しく引用表記をする
著作権侵害を未然に防ぐ習慣
著作権侵害を防ぐためには、日常的に以下を習慣化することが重要です。
-
自分の文章に「なぜ?」を問いかける
-
文章の根拠を確認する
-
必ず一次情報を参照する
-
他人のコンテンツを読むときに「構造」と「表現」を分けて見る
これらの習慣があれば、知らない間に著作権侵害をしてしまうリスクがぐっと減ります。
著作権を守ることは、長期的に見れば最強の「差別化戦略」です。
自分の言葉で語り、オリジナルの価値を提供し続けることで、ファンはあなたに集まり、信頼は深まり、収益は自然とついてきます。
これからコンテンツを販売する方、すでに販売している方も、今日からぜひ意識してみてください。
あなたの文章をチェックしたい人へ
もし「自分の文章が大丈夫か不安…」という方がいれば、AIでチェックする方法もあります。
著作権チェック用おすすめプロンプト
以下のプロンプトを丸っと使ってみてください
プロンプト例
【文章ここに貼る】
ポイント
「依拠性」と「類似性」の観点を入れる
→ 法的に重要な2つの基準だから、AIにもこの2つを意識させる。
「危険性が高い箇所」を具体的に聞く
→ 単に「問題ない」じゃなく、どの部分が怪しいかを明確に。
「改善提案」もセットでお願いする
→ 問題点だけじゃなく、オリジナルにするためのヒントをもらう。
AIで著作権違反チェックをするおすすめツール(2025年版)
実は「著作権侵害を法的に最終判断できるAI」は存在しません。
AIはあくまで参考診断の補助ツールで、最終的な法的責任はユーザー自身にあることを覚えておいてね。
そのうえで、文章の類似度チェック(コピー検出)やオリジナリティ診断に強いおすすめAI系ツールを紹介します。
① Copyleaks
-
特徴
AI搭載の盗用検出ツールで、文書やウェブコンテンツの一致率を調査できる。 -
おすすめポイント
ウェブ上の膨大なデータベースと比較してくれるので、特にブログ記事やnote、電子書籍の盗用チェックに強い。 -
デメリット
詳細な改善提案までは出してくれない。
② Grammarly(Plagiarism Checker 機能)
-
特徴
本来は英語文法チェックツールだけど、有料版に盗用検出機能が付いている。 -
おすすめポイント
SEO目的で英語コンテンツを作る人や、海外ライター向けには最強。 -
デメリット
日本語のチェック精度はそこまで高くない。
③ Turnitin
-
特徴
大学や教育機関向けに開発された盗用検出ツール。 -
おすすめポイント
学術論文レベルの厳密な類似性チェックが可能。精度が高く、ビジネス資料のドラフトや教材チェックにも使える。 -
デメリット
個人では使いにくい(法人契約が多い)。
④ CopyContentDetector(コピペリン)
-
特徴
日本語コンテンツに特化したコピーコンテンツ検出サービス。 -
おすすめポイント
note、Brain、ブログ、LPなどの文章チェックに使える。国内SEO対策にも相性が良い。 -
デメリット
細かい表現改善までは提案してくれない。
⑤ ChatGPT(GPT-4 Turbo以降)
-
特徴
AIに「この文章は著作権侵害の可能性があるか?」とプロンプトを投げることで、依拠性・類似性の観点からアドバイスがもらえる。 -
おすすめポイント
文章の構造分析、改善提案まで一緒に依頼できるのが強み。 -
デメリット
最終的な法的判断ではなく、あくまで補助意見。
結論:おすすめAIツールは?
結論としては
-
まずAI(ChatGPT)で「依拠性」「類似性」を含めたプロンプトでチェック
→ 文章構造と表現の指摘を受ける -
CopyContentDetector(コピペリン)で日本語文章の一致率チェック
-
Copyleaksで追加チェック(特に海外市場向けコンテンツ)
です。
今はAIで表現も変えやすい時代なので
「自分のコンテンツ、他人のものと似通ってない?」と不安な人は
ぜひAIでチェックしてからコンテンツをリリースしましょう!